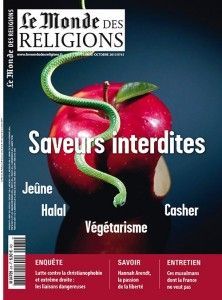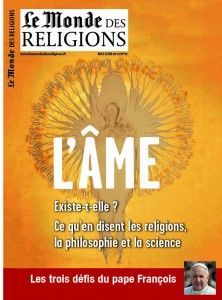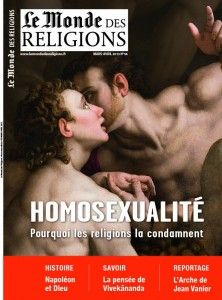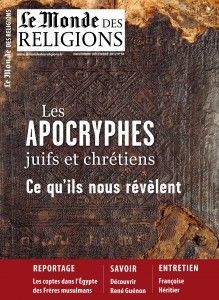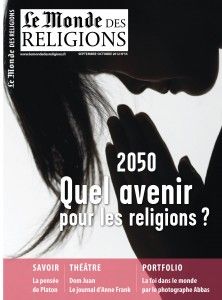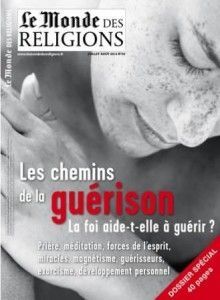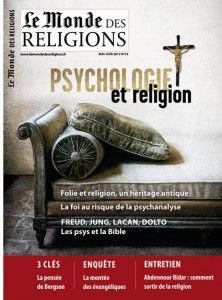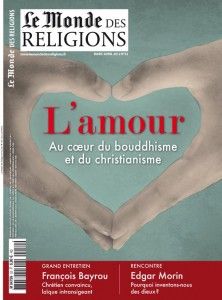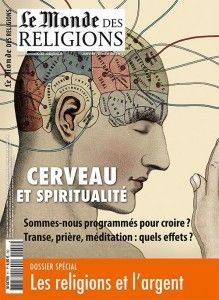社説 宗教の世界
降順でリストされています:最新(2013年11月~12月)から最も古い(2004年11月~12月)まで
保存
保存
『ル・モンド・デ・レリジョン』第62号 – 2013年11/12月号 – 奇跡という問題について、スピノザが『神学政治論』第6章で示唆している考察ほど深遠で啓発的な文章を私は知らない。「人間が人間の知性の及ぶ範囲を超えたあらゆる科学を神聖と呼ぶように、原因が一般的には不明なあらゆる現象に神の手が見られる」と、このオランダの哲学者は記している。ところで、神は自ら定めた自然法則の外で行動することはできない。もし説明のつかない現象が存在するとしても、それは決して自然法則に反するものではない。しかし、複雑な自然法則に関する私たちの知識が未だ限られているため、それらは私たちにとって「奇跡的」あるいは「驚異的」なものに見えるのである。スピノザは、聖書に記された奇跡は伝説的なものか、あるいは私たちの理解を超えた自然現象の結果であると説明する。激しい風の影響で割れたとされる紅海や、人間の肉体や精神のこれまで知られていなかった力を呼び起こしたとされるイエスの治癒などがその例である。そしてスピノザは、奇跡への信仰を政治的に解体し、自らの宗教や国家が「他のすべてのものよりも神にとって尊い」と示そうとする人々の「傲慢さ」を非難する。超自然現象として理解される奇跡への信仰は、彼にとって理性に反する「愚行」であるだけでなく、真の信仰にも反し、信仰を揺るがすものでもある。「したがって、もし自然界にその法則に従わない現象が起こったとすれば、それは必然的にその法則に反し、神が宇宙に普遍的に統制する一般法則を与えることによって確立した秩序を覆すものであると認めざるを得ないであろう。」このことから、奇跡を信じるということは、普遍的な疑念と無神論につながるはずだと結論づけなければなりません。」この社説を書いているのは、私にとって最後の記事となるため、少し感慨深いものがあります。『ル・モンド・デ・レリジョン』の編集長を務め始めてから、実に10年近くが経ちました。いよいよ編集長を退任し、個人的なプロジェクト、つまり書籍、演劇、そして近いうちに映画制作に全力を注ぐ時が来ました。この類まれな出版の冒険に大きな喜びを感じ、皆様のご愛顧に心から感謝申し上げます。おかげさまで、この雑誌はフランス語圏(フランス語圏16カ国で発行)における宗教問題の真の参考誌となりました。皆様のご支援を心より願っております。そして、宗教に関する深い知識と確かなジャーナリズム経験を持つ編集長、ヴィルジニー・ラルースに、編集の指揮を託すことを大変嬉しく思います。彼女は、数名の馴染み深い顔ぶれからなる編集委員会の支援を受けながら、編集委員会のメンバーとして活動していきます。私たちは協力して新しいフォーマットを策定中です。1月号では皆様に、そして次号では彼女自身も発表する予定です。皆様のご多幸をお祈りいたします。『ル・モンド』のオンライン記事はこちら宗教: www.lemondedesreligions.fr [...]
宗教の世界 第61号 – 2013年9/10月 – 聖アウグスティヌスは著書『幸福な人生について』の中でこう記しています。「幸福への欲求は人間にとって本質的なものであり、あらゆる行動の動機となる。世界で最も尊ばれ、最も理解され、最も明確にされ、最も不変のことは、単に幸福になりたいという願望だけでなく、幸福以外の何者でもないと願うということである。これこそが、人間の本性が私たちを駆り立てるものである。」すべての人間が幸福を切望する中で、問題は、この地上に深く永続的な幸福が存在し得るかどうかです。宗教はこの問いに対して、非常に異なる答えを提示しています。私の考えでは、最も対照的な二つの立場は、仏教とキリスト教の立場です。仏陀の教義全体が、今この瞬間における完全な静寂の境地の追求に基づいていますが、キリストの教義は、来世における真の幸福を忠実に約束しています。これは、創始者の生涯――イエスは36歳頃に悲劇的な死を遂げた――に由来するだけでなく、彼のメッセージにも由来しています。イエスが宣言した神の国は地上の国ではなく天の国であり、祝福はこれから来るのです。「悲しむ人々は幸いである。彼らは慰められるからである」(マタイによる福音書5章5節)。ユダヤ教を含め、現世での幸福を求める傾向が強かった古代世界において、イエスは明らかに幸福の焦点を来世へと移しました。この天界への希望は、西洋キリスト教の歴史に深く浸透し、時には様々な形の過激主義へと繋がりました。過激な禁欲主義、殉教への渇望、天界への渇望のための苦行や苦難。しかし、ヴォルテールの有名な言葉「楽園は我が在る所なり」によって、18世紀以降、ヨーロッパにおいて観点の大きな転換が起こりました。楽園はもはや来世で待つものではなく、理性と人間の努力によって地上で実現されるものとなったのです。来世への信仰、ひいては天国の楽園への信仰は徐々に薄れ、現代人の大多数は今この瞬間の幸福を求めるようになるでしょう。その結果、キリスト教の説教は完全に変貌を遂げました。地獄の苦しみと楽園の喜びを強調してきたカトリックとプロテスタントの説教者たちは、今や来世についてほとんど語りません。最も人気のあるキリスト教運動である福音派とカリスマ派は、この新たな現実を全面的に受け入れ、イエスへの信仰こそがまさにこの地上において最大の幸福をもたらすと繰り返し主張しています。そして、現代人の多くが幸福を富と同一視しているため、中には信仰によって地上で「経済的な繁栄」を得られると信者に約束する者さえいます。「金持ちが神の国に入るよりも、らくだが針の穴を通る方がまだ易しい」(マタイ伝 19:24)と宣言したイエスの教えからは、私たちは程遠い存在です。キリスト教の深遠なる真理は、疑いなくこの二つの極端の間にあります。一つは、永遠の命あるいは地獄への恐怖の名の下に、ニーチェが正しく非難したように、生を拒絶し、病的な禁欲主義に走ること。もう一つは、現世の幸福のみを追求することです。イエスは本質的に、現世の快楽を軽蔑せず、「苦行」もしませんでした。飲み食いし、友と分かち合うことを愛していました。私たちはしばしばイエスが「喜びに躍り出る」姿を目にします。しかし、イエスは、至高の至福は現世には見出せないと明言しました。イエスは現世の幸福を拒絶するのではなく、愛、正義、真実といった他の価値を優先させました。こうしてイエスは、愛のため、不正と戦うため、あるいは真実に忠実であり続けるために、現世の幸福を犠牲にして命を捧げることができることを示しました。ガンジー、マーティン・ルーサー・キング、ネルソン・マンデラといった現代の人々の証言は、このことを力強く示しています。疑問は残る。彼らの命という贈り物は、来世で正当な報いを受けるのだろうか?これはキリストの約束であり、世界中の何十億もの信者の希望である。ル・モンド・デ・レリジョン紙の記事はオンラインで読むことができます:www.lemondedesreligions.fr [...]
宗教の世界 第60号 – 2013年7月/8月 – ユダヤ教の伝説によると、神はアダムよりも先にイブを創造しました。楽園で退屈したイブは、神に伴侶を与えてくれるよう願いました。熟考の末、神はついに彼女の願いを聞き入れました。「よろしい。人間を創造しよう。だが気をつけろ、彼はとても敏感だ。あなたが彼より先に創造されたことを彼に決して言ってはならない。彼はひどく怒るだろう。このことは我々の間、つまり女同士の間の秘密にしておきましょう!」もし神が存在するなら、神に性別がないことは明らかです。では、なぜほとんどの主要宗教が神を男性のみで表現してきたのか疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、この号の特集記事が示唆するように、常にそうだったわけではありません。偉大なる女神への崇拝は間違いなく「万軍の主ヤハウェ」への崇拝よりも先行しており、女神たちは初期文明のパンテオンにおいて重要な位置を占めていました。聖職者の男性化は、紀元前3000年の間に起こったこの逆転の主な理由の一つであることは間違いありません。男性によって統治される都市と宗教が、どのようにして異性の至高神を崇拝できるのでしょうか?家父長制社会の発展とともに、この問題は解決しました。至高神、あるいは唯一神はもはや女性として考えられなくなったのです。これは神の表象だけでなく、その性格や機能にも当てはまりました。強さ、支配、権力といった神の属性が重んじられたのです。地上と同様に、天においても世界は支配的な男性によって統治されていました。神の女性的な性格は、様々な神秘主義的・秘教的な潮流を通して宗教の中に生き続けましたが、神の過度な男性化が真に問われたのは近代になってからのことでした。神の表象が男性的から女性的に移行したわけではありません。むしろ、私たちはバランスの再構築を目撃したのです。神はもはや恐るべき裁き主としてではなく、何よりも善良で慈悲深い存在として認識されています。信者たちはますます神の慈悲深い摂理に信頼を寄せています。神の典型的な「父性」的イメージは薄れ、より典型的な「母性」的イメージが主流になりつつあると言えるでしょう。同様に、感受性、感情、そして脆さは、霊的体験において高く評価されています。この変化は、現代社会における女性の再評価と明確に結びついており、特に女性が礼拝において教えや指導の立場に就くことを認めるなど、宗教にもますます影響を与えています。また、現代社会において、思いやり、寛容さ、歓迎の精神、そして生命の保護といった、より「典型的に」女性的とされる資質や価値観が認識されていることも反映しています。たとえそれが女性だけでなく男性にも明らかに関係するものであってもです。あらゆる宗教原理主義者の間でマッチョイズムが驚くほど再燃している現状を目の当たりにし、私は、この女性の再評価と神の女性化こそが、宗教における真の精神的刷新の鍵となると確信しています。女性は疑いなく神の未来です。この機会に、私たちの忠実な読者の皆様によく知られている二人の女性に敬意を表したいと思います。貴誌の元編集長、ジェニファー・シュワルツ氏が新たな冒険に乗り出されます。5年以上にわたり、その職務に情熱と寛大さをもって尽力されたことに、心から感謝申し上げます。また、後任のヴィルジニー・ラルース氏を温かく歓迎いたします。ラルース氏は長年にわたり宗教専門の学術誌を監修し、ブルゴーニュ大学で宗教史を教えられました。また、長年にわたり『ル・モンド・デ・レリジョン』誌に寄稿していただいています。. [...]
『ル・モンド・デ・レリジョン』第59号 – 2013年5/6月号 – フランス2の生中継でこの出来事についてコメントするよう招かれ、新教皇がホルヘ・マリオ・ベルゴリオ氏であることを知った時、私の即座の反応は、これは真にスピリチュアルな出来事だ、というものでした。ブエノスアイレス大司教について初めて聞いたのは、約10年前、ピエール神父からでした。彼はアルゼンチンへの旅行中、壮麗な司教館を後にして質素なアパートに住み、一人でスラム街に出かけることが多かったこのイエズス会員の素朴さに感銘を受けたのです。アッシジの貧者を彷彿とさせるフランシスコという名前が選ばれたことは、私たちがカトリック教会の重大な変化を目撃しようとしていることを改めて示すものでした。教義の変化ではなく、おそらく道徳観の変化でもなく、教皇制の概念そのもの、そして教会の統治様式の変化なのです。サン・ピエトロ広場に集まった数千人の信者に「ローマ司教」と名乗り、共に祈る前に群衆に祈りを捧げるよう求めたフランシスコは、わずか数分間で、数々の身振りを通して、自らの役割に対する謙虚な認識に立ち返る意志を示した。この認識は、ローマ司教をキリスト教世界の普遍的な首長であるだけでなく、世俗国家の長である真の君主とさえ考えていなかった初期キリスト教徒の認識を想起させる。選出以来、フランシスコは慈善活動を積み重ねてきた。今、彼が待ち受ける教会刷新という壮大な課題において、どこまで尽力するのかという疑問が浮上する。30年以上にわたりスキャンダルに揺れてきたローマ教皇庁とバチカン銀行を、ついに改革するのだろうか?教会のための合議制統治システムを導入するのだろうか?かつての教皇領時代の遺産であるバチカン市国の現状を維持しようとするのでしょうか。これはイエスの貧困の証言と世俗権力の拒絶とは全く矛盾するものです。教皇は、また、彼が深く関心を寄せているエキュメニズムや諸宗教対話の課題に、どのように取り組むのでしょうか。そして、教会の言説と人々の生活、特に西洋における生活の溝が広がり続ける中で、福音宣教はどうするのでしょうか。確かなことが一つあります。フランシスコは、文化の多様性、そしてあらゆる被造物(おそらく初めて、動物たちに思いやりのある教皇がいます!)を尊重する世界平和を支持するという当初の宣言に見られるように、この福音の偉大な息吹をカトリック世界とその先にもたらすために必要な、心と知性、そしてカリスマ性さえも備えています。選出直後、イエズス会の若き長老時代に旧軍事政権と共謀していたとの非難を浴びた激しい批判は、数日後には収束した。特に、同郷でノーベル平和賞受賞者のアドルフォ・ペレス・エスキベル氏が、軍事政権によって14ヶ月間投獄され拷問を受けた後、新教皇は他の聖職者とは異なり「独裁政権とは何の関係もない」と述べたことが、その一因となった。フランシスコはこうして、大胆な行動に出られるだけの猶予期間を得ている。ただし、選出からわずか1ヶ月足らずで謎めいた死を遂げ、多くの希望を抱かせたヨハネ・パウロ1世と同じ運命を辿らないことが条件である。フランシスコが信者たちに祈りを捧げるよう呼びかけるのは、間違いなく正しい。www.lemondedesreligions.fr [...]
ル・モンド・デ・レリジョン第58号 – 2013年3/4月 – フランスで同性婚をめぐる議会の白熱した議論を受けて、今号の大部分を宗教が同性愛をどう捉えているかという問題に割いていることに、読者の中にはきっと違和感を覚える方もいるでしょう。もちろん、この議論の核心部分、特に親子関係の問題については、第2部で、フランスの首席ラビ、ジル・ベルンアム氏、哲学者オリヴィエ・アベル氏とティボー・コラン氏、精神分析医で民族学者のジュヌヴィエーヴ・ドゥレシ・ド・パルセヴァル氏、そして社会学者ダニエル・エルヴュー=レジェール氏といった対照的な視点から論じています。しかし、私には、これまで大きく見過ごされてきた重要な問題があるように思われます。それは、宗教は同性愛についてどう考え、何世紀にもわたって同性愛者をどのように扱ってきたのか、ということです。この問いは、ほとんどの宗教指導者自身によって回避され、神学や宗教法ではなく、人類学や精神分析の領域に即座に位置づけられました。その理由は、同性愛がほとんどの聖典で激しく批判されていること、そして同性愛者が依然として世界の多くの地域で宗教の名の下にどのように扱われているかを詳しく調べれば、より明確になります。古代では同性愛は概ね容認されていましたが、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖典では、重大な倒錯行為として描かれています。「男が女と寝るように男と寝るなら、その行為は忌まわしい。彼らは必ず死刑に処せられ、その血は彼らに帰せられる」とレビ記に記されています(レビ記20章13節)。ミシュナーもこれと全く同じことを述べており、教父たちもこの行為を厳しく非難することができませんでした。トマス・アクィナスの言葉を借りれば、この行為は「神を冒涜する」ものであり、彼の目には、全能の神が定めた自然の秩序そのものを侵害するものと映ったからです。敬虔なキリスト教信者であったテオドシウス帝とユスティニアヌス帝の治世下において、同性愛者は死刑に処せられ、悪魔と共謀したと疑われ、自然災害や疫病の責任を問われました。コーランは約30節でこの「不自然」で「非道な」行為を非難しており、シャリーア法は今日でも同性愛者に対し、懲役刑から絞首刑、さらには鞭打ち刑まで、国によって異なる刑罰を科しています。アジアの宗教は一般的に同性愛に対して寛容ですが、仏教共同体の戒律である律法(ヴィナヤ)やヒンドゥー教の一部の宗派では同性愛が非難されています。ユダヤ教およびキリスト教の諸機関の立場は近年かなり軟化しているものの、依然として約100カ国で同性愛は犯罪または違法行為とみなされており、若者の自殺の主な原因となっています(フランスでは、20歳未満の同性愛者の3人に1人が社会的拒絶を理由に自殺を試みた経験があります)。私たちが強調したいのは、宗教的議論によって数千年にわたり煽られてきたこの暴力的な差別です。結婚だけでなく、家族についても複雑かつ本質的な議論が続いています(真の問題は同性カップルと異性カップルの市民権の平等ではなく、親子関係や生命倫理の問題であるため)。この議論は同性カップルの要求を超え、養子縁組、医療補助による生殖、代理出産といった問題にも関わっており、異性カップルにも同様に影響を及ぼす可能性があります。政府は賢明にも、国家倫理委員会の意見を求め、この議論を秋まで延期しました。これらは実に重大な問題であり、「これは私たちの社会を混乱させている」(実際にはすでに混乱している)とか、逆に「これは世界の避けられない流れだ」といった単純な議論では避けることも解決することもできない。いかなる発展も、人類と社会にとって何がよいかという観点から評価されなければならないのだ。http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/58/ [...]
『ル・モンド・デ・レリジョン』第57号(2013年1月/2月号) 個人が「自らの精神的な道を見つける」ことができるという考えは、極めて現代的なものでしょうか?答えはイエスでもありノーでもあります。東洋では、仏陀の時代に、絶対者を求め、個人的な解放への道を探し求めていた人々が数多くいました。古代ギリシャ・ローマでは、ピタゴラス派から新プラトン主義者、ストア派やエピクロス派を含む数多くの秘儀信仰や哲学学派が、豊かな人生を求める個人に、多くの入門の道や叡智への道を提供しました。その後、個人と集団の生活に意味を与える宗教を基盤とする主要な文明が発展し、精神的な提供は限定的なものとなりました。しかしながら、それぞれの主要な伝統の中には、個人の多様な期待に応える多様な精神的潮流が常に存在し続けるのです。このように、キリスト教においては、数多くの修道会が多様な精神的感受性を提供しています。カルトジオ会やカルメル会のような最も観想的な修道会から、ドミニコ会やイエズス会のような最も知的な修道会、あるいは貧困(フランシスコ会)、労働と祈りのバランス(ベネディクト会)、慈善活動(聖ビンセント・ド・ポール宣教修道会)を重視する修道会まで、多岐にわたります。宗教生活に身を捧げる人々以外にも、中世後期以降、一般信徒の団体が発展しました。彼らは多くの場合、主要な修道会の影響圏内で生活していましたが、ベギン会が受けた迫害からもわかるように、必ずしも主要な修道会から高く評価されていたわけではありませんでした。イスラム教においても同様な現象が見られ、多くのスーフィーの兄弟団が発展しましたが、その中には迫害を受けたものもありました。ユダヤ教の神秘主義的感受性はカバラの誕生に表れ、アジアでは多種多様な精神的流派や運動が繁栄を続けました。近代は二つの新たな要素をもたらしました。集団宗教の衰退と文化の融合です。これは、意味を求める各個人の個人的な願望と結びついた新たな精神的融合と、いかなる宗教的信念や慣習にもとらわれない世俗的な精神性の発展をもたらしました。この状況は古代ローマを彷彿とさせるものであり、全く前例のないものではありません。しかし、文化の融合ははるかに激しくなっています(今日、誰もが人類の精神的遺産のすべてにアクセスできるのです)。そして、もはや社会エリート層に限定されない、精神的探求の真の民主化も目の当たりにしています。しかし、こうしたあらゆる変革を通して、一つの本質的な問いが残ります。それは、各個人が自分自身を最大限に満たすことができる精神的な道を求めるべきなのか、そして見つけることができるのか、ということです。私の答えは間違いなく「イエス」です。昔も今も、精神的な道は個人の旅の成果であり、各人が自分の感受性、能力、野心、願望、そして疑問に合った道を求めるならば、この旅はより成功する可能性が高いのです。もちろん、現代社会には多様な道があり、迷ってしまう人もいます。かつてダライ・ラマは「最良の精神的な道とは何か?」と尋ねられました。チベットの指導者はこう答えました。「あなたをより良い人間にしてくれる道です。」これは間違いなく、識別力を高めるための優れた基準です。http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/57/ 保存 [...]
宗教の世界 第56号 – 2012年11/12月 – 神を狂信する者たちがいる。彼らは自らの宗教の名の下に殺人を犯す。カナン人の虐殺を命じたモーセから、カトリックの大審問官を経たアルカイダのジハード主義者に至るまで、宗教的狂信は一神教の中で様々な形をとるが、常に根底にあるのは同じである。殺人、あるいは殺人を命じるのは、血統や信仰の純粋さを守るため、コミュニティ(あるいはブレイビクの場合のように文化さえも)を脅かす者から守るため、そして宗教の社会における影響力を拡大するためである。宗教的狂信は、人間に他者を尊重するよう啓蒙することを主眼とする聖書とコーランの教えから大きく逸脱している。これこそが、コミュニタリアニズムが醸し出す毒です。人々、組織、コミュニティへの帰属意識がメッセージそのものよりも重要になり、「神」は自己防衛と支配のための単なる言い訳に成り下がってしまうのです。宗教的狂信は、2世紀以上も前に啓蒙思想家たちによって徹底的に分析され、非難されました。彼らは、依然として宗教に支配された社会において、良心と表現の自由が存続できるよう闘いました。彼らのおかげで、私たち西洋人は今日、信じるか信じないかだけでなく、宗教を批判し、その危険性を糾弾する自由も得ています。しかし、この闘争と、苦労して勝ち取った自由によって、これらの同じ哲学者たちが、すべての人が同じ政治的空間の中で調和して生きられるよう目指していたことを忘れてはなりません。したがって、知的表現の自由であれ芸術的表現の自由であれ、表現の自由は、単に紛争を誘発したり煽ったりするためだけに他者を攻撃することを意図したものではないのです。さらに、ジョン・ロックは、社会平和の名の下に、最も過激な無神論者でさえ、最も強硬なカトリック教徒と同様、公の場で沈黙させられるべきだと信じていた。今日、イスラム教信者にとって最も神聖なもの、すなわち預言者の姿を攻撃し、西洋とイスラム世界の間の緊張を煽ることだけを目的として、芸術的に嘆かわしい映画を制作し、オンラインで配信する者たちに、ロックは何と言うだろうか。新聞を売るためにムハンマドの新しい風刺画を出版し、世界中の多くのイスラム教徒の間でまだくすぶっている怒りの残り火を煽り、火に油を注ぐ者たちに、ロックは何と言うだろうか。そして、その結果はどうなっているだろうか。死者、イスラム諸国におけるキリスト教徒の少数派への脅威の増大、そして世界中の緊張の高まりである。表現の自由のための闘いは、いかに崇高なものであっても、地政学的な視点から状況を分析する必要性を否定するものではありません。過激派グループは、イメージを悪用して共通の敵、つまり映画的な空想と戯画に矮小化された西洋に人々を結集させようとしています。私たちは、世界平和を脅かす数々の緊張にさらされながら、相互に繋がり合った世界に生きています。啓蒙思想家たちが国家レベルで提唱したものは、今や世界規模でも通用するものです。信者を怒らせ、その中でも最も過激な者を刺激することだけを目的とした戯画的な批判は、愚かで危険です。その主な効果は、宗教狂信者の陣営を強化し、文化と宗教の間の建設的な対話を築こうとする人々の努力を損なわせることです。自由とは、責任と公共の利益への配慮を意味します。これらがなければ、いかなる社会も存続できません。http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2012/56/ [...]
宗教の世界 第55号 – 2012年9/10月号 — 約30年前、私が宗教社会学と宗教史の研究を始めた頃、話題の中心は「世俗化」だけでした。宗教研究の専門家の多くは、物質主義と個人主義が強まるヨーロッパ社会において、宗教は徐々に変容し、やがて消滅していくと考えていました。そして、西洋の価値観とライフスタイルのグローバル化に伴い、ヨーロッパのモデルが世界に広まるだろうと。つまり、宗教は多かれ少なかれ長期的には滅亡の運命にあったのです。しかし、ここ10年ほどで、このモデルと分析は逆転しました。「脱世俗化」が語られ、アイデンティティに基づく保守的な宗教運動が至る所で台頭し、アメリカの偉大な宗教社会学者ピーター・バーガーは「世界は今も昔も変わらず、猛烈に宗教的である」と述べています。ヨーロッパは世界的に例外とみなされていますが、この新たな宗教の波の影響をますます受けやすい国です。では、未来のシナリオはどうなるのでしょうか?鋭い観察者たちは、現在の傾向に基づき、本号の詳細な特集記事で、2050年の世界宗教のあり得る展望を提示しています。キリスト教は、特に発展途上国の人口動態に加え、五大陸全土における福音派とペンテコステ派の力強い成長によって、他の宗教に対するリードを広げるでしょう。イスラム教は人口増加によって成長を続けるものの、特にヨーロッパとアジアではその成長は大幅に鈍化すると予想されており、キリスト教よりもはるかに少ない改宗者しかいないイスラム教の拡大は、最終的に抑制されるでしょう。ヒンドゥー教と仏教は、後者の価値観や特定の実践(瞑想など)が西洋とラテンアメリカでますます広まるとしても、比較的安定した状態を維持するでしょう。血縁関係に結びついた他のごく少数の宗教と同様に、ユダヤ教も様々な人口動態のシナリオと異人種間の結婚の数によって、安定を維持するか衰退するかのどちらかになるでしょう。しかし、ジャン=ポール・ウィレームとラファエル・リオジエがそれぞれ独自の方法で私たちに示唆しているように、こうした広範な傾向を超えて、宗教は近代性、特に個人化とグローバリゼーションによって変容し、影響を受け続けるでしょう。今日、個人は宗教についてますます個人的な見解を持ち、時には融合し、しばしば寄せ集めの、独自の意味の枠組みを作り上げています。原理主義や統合主義の運動でさえ、個人、あるいは個人の集団が、再創造された「純粋な起源の宗教」を寄せ集めた産物です。グローバリゼーションのプロセスが続く限り、宗教は、アイデンティティを欠き、不安を抱え、文化的侵略や支配を受けていると感じている個人に、アイデンティティの基準点を提供し続けるでしょう。そして、人類が意味を探し求める限り、人類の広大な宗教的遺産の中に答えを求め続けるでしょう。しかし、こうしたアイデンティティと精神性の探求は、もはや過去のように、不変の伝統や規範的な制度的枠組みの中で経験できるものではありません。したがって、宗教の未来は、信者の数だけでなく、過去の遺産をいかに再解釈するかにもかかっています。そして、まさにこれこそが、長期的な展望に基づく分析を危険にさらす最大の疑問符なのです。ですから、理性に欠ける私たちは、常に想像し、夢を見ることができます。そして、まさにこの疑問を、今号のコラムニストを通して皆さんにお届けします。彼らは、「2050年に向けて、あなたはどんな宗教を夢見ていますか?」という問いに答えることに同意してくれました。 [...]
宗教の世界 第54号 – 2012年7/8月号 — 信仰と治癒の相関関係を示す科学的研究が増えており、太古の昔から観察されてきた事実を裏付けています。思考する動物である人間は、信頼の度合いに応じて、生、病気、そして死に対して異なる関係性を持っています。自信、セラピスト、科学、神への信頼、そしてプラセボ効果などから、重要な疑問が生じます。信仰は治癒を助けるのでしょうか?祈りや瞑想などを通して、心は治癒のプロセスにどのような影響を与えるのでしょうか?医師自身の信念は、患者へのケアとサポートにおいてどれほど重要なのでしょうか?これらの重要な疑問は、病気とは何か?「治癒」とはどういう意味か?といった本質的な問いに新たな光を当てます。結局のところ、治癒とは常に自己治癒です。治癒をもたらすのは、病人の心身です。細胞再生を通して、体は失われたバランスを取り戻すのです。治療的介入や薬物療法を通して病んだ体を支えることは、しばしば有益であり、必要でさえあります。しかし、これらは患者の自己治癒プロセスを助けるに過ぎません。心理的側面、信念、士気、そして人間関係も、この治癒プロセスにおいて重要な役割を果たします。したがって、治癒プロセスには患者全体が関わっています。心身のバランスを取り戻すには、患者が健康を取り戻そうと真摯に決意し、受けているケアを信頼し、そして場合によっては人生全般や、自分を助けてくれる慈悲深い高次の力への信頼を持たなければなりません。同様に、時には治癒、つまりバランスを取り戻すには、患者の環境、つまり生活ペースやライフスタイル、食事、呼吸法やボディケアの習慣、そして感情面、友人関係、そして職業上の人間関係の変化が不可欠です。なぜなら、多くの病気は、患者の生活におけるより全体的な不均衡の局所的な症状であるからです。患者がこのことに気づかなければ、次々と病気を繰り返したり、慢性疾患やうつ病などに苦しんだりすることになります。治癒への道が私たちに教えてくれるのは、人間を機械のように扱うことはできないということです。曲がった車輪やパンクしたタイヤを交換する自転車の修理のように扱うことはできません。病気に表れるのは、その人の社会的、感情的、そして精神的な側面であり、治療においては、この全体的な側面を考慮に入れなければなりません。私たちがこのことを真に理解しない限り、フランスは今後長きにわたり、抗不安薬や抗うつ薬の消費量、そして社会保障制度の赤字において世界一であり続ける可能性が高いでしょう。 [...]
宗教の世界 第53号 – 2012年5/6月号 — 今日、人々の関心は、アイデンティティの探求、自らの文化的ルーツの再発見、そして共同体の結束へと移っています。そして悲しいことに、ますます、自己への引きこもり、他者への恐怖、道徳的硬直性、そして偏狭な教条主義にも傾倒しつつあります。世界のいかなる地域も、いかなる宗教も、このアイデンティティと規範への回帰という広大な地球規模の動きから逃れることはできません。ロンドンからカイロ、デリー、ヒューストン、エルサレムを経て、女性のベールやかつら着用、厳格な説教、そして教義の守護者の勝利へと向かう傾向が見られます。1970年代後半に私が経験したこととは対照的に、いまだに宗教に関心を持つ若者の多くは、叡智への渇望や自己探求よりも、確固たる基準への欲求、そして祖先の伝統に根ざしたいという願望に突き動かされています。幸いなことに、この傾向は避けられないものではありません。それは、制御不能なグローバリゼーションの行き過ぎと、私たちの社会の残酷な個人主義への解毒剤として生まれました。それはまた、非人間的な経済自由主義と道徳の急速な自由化への反動でもありました。したがって、私たちはまさに典型的な振り子の揺れを目撃しています。自由の後には法。個人の後には集団。変化のユートピア的ビジョンの後には、過去のモデルの安心感。このアイデンティティへの回帰には健全な何かがあることを私は喜んで認めます。自由至上主義的で消費主義的な個人主義の行き過ぎの後、社会的な絆、法、そして美徳の重要性を再発見するのは良いことです。私が嘆かわしいのは、最近の宗教回帰のほとんどが過度に硬直的で非寛容な性質を持っていることです。共同体主義に陥ることなく共同体に再統合することは可能です。宗派主義に陥ることなく偉大な伝統の古来の教えを守り、道徳的にならずに高潔な人生を送りたいと願うことは可能です。こうした硬直した態度に対し、幸いなことに宗教自体の中に解毒剤があります。それは精神性です。信者が自らの伝統を深く掘り下げれば掘り下げるほど、心に触れ、心を開く知恵の宝庫を発見するでしょう。そして、すべての人間は兄弟姉妹であり、暴力や他者への批判は宗教の戒律を破ることよりも重大な罪であることを思い出させてくれるのです。宗教的不寛容と共同体主義の台頭は私を不安にさせますが、宗教そのものを心配しているわけではありません。宗教は確かに最悪の事態をもたらす一方で、最善の事態ももたらしうるからです。 [...]
宗教の世界 第52号 – 2012年3/4月号 — フランス人が宗教に基づいてどのように投票しているかという問題は、ほとんど取り上げられていません。世俗主義の原則により、第三共和政開始以来、国勢調査で宗教的所属は問われていませんが、この問題に関する情報を提供する世論調査は存在します。しかし、サンプル数が非常に少ないため、ユダヤ教、プロテスタント、仏教など、信者数がそれぞれ100万人未満と非常に少ない少数派の宗教を測定することはできません。しかし、カトリック教徒(フランス人口の約60%、うち25%がカトリック教徒)とイスラム教徒(約5%)、そして「無宗教」と自認する人々(フランス人口の約30%)の投票パターンについては、明確な情報を得ることができます。昨年1月に実施されたソフレ/ペレラン誌の世論調査は、フランスのカトリック教徒の歴史的な右翼的傾向を裏付けている。第1回投票では、33%のカトリック教徒がニコラ・サルコジに投票し、この数字はカトリック教徒の信仰者の間では44%に上昇する。21%はマリーヌ・ル・ペンにも投票するが、この数字は信仰者カトリック教徒の全国平均(18%)より低い。第2回投票では、53%のカトリック教徒がニコラ・サルコジに投票するのに対し、フランソワ・オランドには47%が投票し、信仰者カトリック教徒の67%が右翼候補に投票し、定期的に教会に通う信者に限っては75%にも上る。この世論調査ではまた、カトリック教徒は雇用の安定と購買力を優先する点で平均的なフランスの有権者と一致しているものの、不平等と貧困の削減については他の人々ほど関心がなく、犯罪との戦いについてはより関心があることも明らかになった。実際のところ、候補者がカトリック教徒であるかどうかはほとんど問題ではない。注目すべきは、カトリック教徒であることを公言している唯一の主要大統領候補であるフランソワ・バイルーが、カトリック教徒からの票を他の国民と比べてそれほど獲得していないことである。フランスのカトリック教徒の多く、特に信仰を重んじる人々は、秩序と安定に基づく価値観を主に支持している。しかし、フランソワ・バイルーは、根本的な倫理的意味合いを持つ様々な社会問題に関して進歩的な見解を持っている。これは、伝統的なカトリック教徒の有権者の相当部分を動揺させる可能性が高い。ニコラ・サルコジは間違いなくこれを察知しており、生命倫理法、同性親子関係、同性婚に関して伝統的なカトリック教徒の立場を堅持している。最後に、政治学院政治研究センターが実施した調査によると、フランスのイスラム教徒はカトリック教徒とは異なり、圧倒的に左派政党に投票している(78%)。彼らの4分の3が低技能職に就いているにもかかわらず、宗教と特に関連した投票パターンが顕著です。イスラム教徒の労働者と従業員の48%が左派であると自認しているのに対し、カトリック教徒の労働者と従業員は26%、無宗教の労働者と従業員は36%です。「無宗教」人口全体(増加傾向にあります)も、左派に強く投票しています(71%)。これは、社会問題に関しては進歩的であることが多い「無宗教」と、同じ問題に関しては間違いなくより保守的であるものの、「サルコジとは無縁」の精神を貫くフランスのイスラム教徒との間に、奇妙な連携があることを示唆しています。. [...]
『宗教の世界』第51号 – 2012年1月/2月号 – この特集は、重要な事実を浮き彫りにしています。祈り、シャーマニック・トランス、瞑想といった多様な形態の霊的体験は、脳に身体的痕跡を残すのです。この事実から生じる哲学的議論や、唯物論的あるいは心霊主義的な解釈を超えて、私はこの事実からもう一つの教訓を導き出します。それは、霊性とは何よりもまず、身体だけでなく精神にも触れる生きた体験であるということです。それぞれの文化的背景によって、霊性は神との出会い、言い表せない力や絶対者との出会い、精神の神秘的な深淵との出会いなど、非常に異なる対象や表象を指します。しかし、これらの表象には常に、深い内なる平和、意識の拡大、そして多くの場合、心の拡大を喚起するという共通の糸口があります。神聖なものは、どのような名前や形で与えられようとも、それを体験する者を変容させます。そして、それは感情体、精神、そして魂といった存在全体に深く影響を与えます。しかし、多くの信者はこうした経験を持っていません。彼らにとって宗教は、主に個人および集団のアイデンティティの指標であり、道徳規範であり、遵守すべき一連の信念と規則です。つまり、宗教は社会的・文化的側面に矮小化されているのです。宗教のこの社会的側面が現れ、徐々に個人的な経験を覆い隠していった時期を、歴史の中に特定することができます。それは、人類が自然と共存していた遊牧生活から、都市が建設され、意識の変容を通して自然の精霊との接触を確立していた定住生活への移行です。定住生活では、都市が築かれ、意識の変容を通して自然の精霊との接触が確立されましたが、その神々に犠牲が捧げられました。「犠牲」という言葉の語源である「神聖なものにする」という言葉自体が、神聖なものがもはや経験されないことを明確に示しています。それは、世界秩序を保証し、都市を守るための儀式的な行為(神への捧げ物)を通して行われます。そして、この任務は、今や大勢となった民衆によって、専門の聖職者に委任されています。このように、宗教は本質的に社会的かつ政治的な側面を帯びるようになります。つまり、共通の信念、倫理規範、そして儀式を軸に、絆を築き、共同体を結束させるのです。こうした過度に外在的で集団的な側面への反応として、紀元前1千年紀中頃、あらゆる文明において多様な賢者が現れ、神聖なものの個人的な体験の復興を模索しました。中国の老子、インドのウパニシャッドの著者やブッダ、ペルシャのゾロアスター教、ギリシャの秘儀カルトの創始者やピタゴラス、そしてイスラエルの預言者たちからイエスに至るまでがそうです。こうした精神的な運動は、しばしば宗教的伝統の中で発生し、宗教を内側から揺さぶることで変革していく傾向があります。世界中の多様な文化を横断するこの驚異的な神秘主義の高まりは、その収束と共時性で歴史家を驚かせ続けています。そして、個人的な側面を導入することで、宗教を変革しつつあります。この個人的な側面は、多くの点で原始社会における根源的な神聖な体験と再び結びつくのです。そして、現代がこの古代にどれほど似ているかに私は驚嘆します。まさにこの側面こそが、現代人がますます関心を寄せているものです。彼らの多くは、宗教を冷たく、社会的なもの、そして外的なものとみなし、宗教から距離を置いてきました。これは、最も古風な聖なる形態、つまり「創造される」というよりもむしろ経験される聖なるものと再び繋がろうとする超近代主義のパラドックスです。したがって、21世紀は、急速なグローバリゼーションによって生み出された恐怖に直面し、アイデンティティが復活したことで宗教的であると同時に、宗教的であるか否かに関わらず、多くの個人が経験と変容を求めていることで精神的な世紀でもあるのです。. [...]
宗教の世界 第50号 – 2011年11/12月号 — 2012年12月21日に世界は終わるのでしょうか? 長い間、私はマヤ文明の有名な予言には注目していませんでした。しかし、ここ数ヶ月、多くの人々からこのことについて質問を受けるようになりました。インターネットで読んだ情報や、ハリウッドの大災害映画『2012』の影響で、十代の子供たちが不安に陥っているという話もよく聞きます。マヤの予言は本物なのでしょうか? ウェブ上で読めるような、世界の終わりが差し迫っているという他の宗教的予言はあるのでしょうか? 宗教は終末について何を語っているのでしょうか? 今号の特集記事では、これらの疑問に答えます。しかし、2012年12月21日をめぐるこの噂が広まったことで、別の疑問が浮かび上がります。それは、私たちの同時代人の多くが、ほとんどが無宗教で、このような噂がもっともらしく思えるにもかかわらず、この不安をどう説明できるのか、ということです。私には2つの説明が考えられます。まず第一に、私たちは人類が暴走列車に乗っているかのような、極めて悲惨な時代を生きています。実際、いかなる機関も、いかなる国家も、新自由主義資本主義の庇護の下で消費主義イデオロギーと経済のグローバル化が私たちを未知なる世界、ひいては深淵へと突き落としているこの突進を止めることはできないようです。劇的な不平等の拡大、地球全体を脅かす環境破壊、世界経済全体を弱体化させている制御不能な金融投機。そして、私たちのライフスタイルの激変は、西洋人を根こそぎ忘れた記憶喪失者に変え、未来への展望を描けなくしています。私たちのライフスタイルは、過去3000年から4000年よりも、間違いなく過去1世紀の間に大きく変化しました。かつてのヨーロッパ人は主に田舎で暮らし、自然を観察し、ゆったりとしたペースで緊密な農村世界に根ざし、古くからの伝統に深く根ざしていました。中世や古代の人々も同様でした。今日のヨーロッパ人は圧倒的に都市化が進んでおり、地球全体との繋がりを感じているものの、強い地域との繋がりは希薄です。彼らは目まぐるしいペースで個人主義的な生活を送り、祖先から受け継がれた古来の伝統からしばしば切り離されています。私たちが現在経験しているような急進的な革命は、新石器時代(近東では紀元前1万年頃、ヨーロッパでは紀元前3000年頃)まで遡らなければ、おそらく見つけることができません。人類が遊牧民的な狩猟採集生活を捨て、村落に定住し、農業と畜産を発展させた時代です。これは私たちの精神に深刻な影響を及ぼします。この革命のスピードは、不確実性、根本的な指針の喪失、そして社会的な絆の弱化を生み出しています。個人と人間社会の両方にとって、不安、不安、そして混乱した脆弱性の源となり、破壊、崩壊、絶滅といったテーマに対する感受性を高めています。一つ確かなことがあります。それは、私たちが経験しているのは世界の終わりの兆候ではなく、一つの世界の終わりだということです。私が今述べた数千年の歴史を持つ伝統的な世界、そしてそれに伴うあらゆる思考パターン。しかし同時に、私たちが今も浸りきっている、その伝統に続く超個人主義的かつ消費主義的な世界も存在します。この世界は疲弊の兆候を露呈し、人類と社会の真の進歩にとって真の限界を露呈しています。ベルクソンは、新たな課題に立ち向かうには「魂の補充」が必要だと述べました。実際、この深刻な危機の中に、予測されていた一連の生態学的、経済的、そして社会的大惨事だけでなく、意識の覚醒と個人および集団の責任感の研ぎ澄まされた感覚を通して、再生、ヒューマニズム的かつ精神的な再生の機会も見出しているのです。. [...]
宗教の世界 第49号 – 2011年9/10月号 — あらゆる種類の原理主義と共同体主義の強化は、9/11の主要な影響の一つです。この悲劇は、世界的な反響とともに、イスラム教と西洋の分断を露呈させ、さらに悪化させました。それは、過去数十年間の超急速なグローバル化と、その結果生じた文化衝突に関連するあらゆる恐怖の兆候であり、同時に促進剤でもありました。しかし、アイデンティティに基づくこれらの緊張は、依然として懸念を引き起こし、メディア報道を絶えず煽り立てています(7月のオスロ虐殺はその最新の例の一つです)。しかし、9/11のもう一つの、全く逆の影響、すなわち、狂信を生み出す一神教の拒絶という問題を覆い隠しています。ヨーロッパで最近行われた世論調査は、一神教が現代人にとってますます恐怖の対象になっていることを示しています。今では「平和」や「進歩」という言葉よりも、「暴力」や「退行」という言葉の方が、彼らと結び付けられやすくなっています。宗教的アイデンティティの復活と、それに伴う狂信的な行為がもたらした結果の一つが、無神論の急増です。この運動は西洋諸国でも広く見られますが、特にフランスでは顕著です。無神論者の数は10年前の2倍に増加し、フランス人の大多数が無神論者または不可知論者を自認しています。もちろん、この不信感と宗教への無関心の急増の原因はより深く、本報告書ではそれらを分析しています。批判的思考と個人主義の発達、都市生活、宗教の伝承の衰退などが挙げられます。しかし、現代の宗教的暴力が、宗教離れという広範な現象を悪化させていることは間違いありません。この現象は、狂信者の殺人的な狂気に比べればはるかに目立たないものです。「倒れる木の音は、成長する森の音をかき消す」という古い諺が当てはまるかもしれません。しかし、それらが当然私たちを不安にさせ、短期的には世界平和を脅かすため、私たちは原理主義や共同体主義の復活に過度に注目し、長期的な歴史的規模で真の変革が起こっていることを忘れています。これは、あらゆる階層の人々における宗教と古来からの神への信仰の根深い衰退こそが、真の変革であるという事実を忘れています。この現象はヨーロッパに特有で、特にフランスで顕著だと言う人もいるでしょう。確かにその通りですが、この現象は激化し続けており、その傾向はアメリカ東海岸にも広がり始めています。教会の長女であったフランスは、宗教的無関心の長女になる可能性も十分にあります。アラブの春はまた、個人の自由への希求が普遍的であり、その最終的な帰結として、イスラム世界においても西洋世界においても、個人の宗教からの解放、そしてニーチェが予言した「神の死」をもたらす可能性を示唆しています。教義の守護者たちは、このことを明確に理解し、個人主義と相対主義の危険性を絶えず非難してきました。しかし、信じる自由、考える自由、そして自らの価値観や人生に与えたい意味を選択する自由といった、人間の根源的な欲求を抑圧することはできるのでしょうか?長期的には、宗教の未来は、数千年にわたってそうであったように、集団としてのアイデンティティや集団への個人の服従ではなく、個人の精神的な探求と責任にあるように思われます。私たちがますます陥りつつある無神論と宗教拒絶の局面は、もちろん、消費主義の蔓延、他者への無関心、そして新たな形の野蛮さへとつながりかねません。しかし同時に、それは世俗的であろうと宗教的であろうと、私たち皆が希求する偉大な普遍的価値、すなわち真実、自由、そして愛に真に根ざした、新たな形の精神性への序章となる可能性もあるのです。そうすれば、神、あるいはむしろ、神の伝統的な表象のすべてが、無駄死にすることはなくなるでしょう。. [...]
『ル・モンド・デ・リジョナルズ』第48号 – 2011年7/8月号 — DSK事件が波紋を呼び、多くの議論や疑問を巻き起こし続けている中、ソクラテスが若きアルキビアデスに伝えた教訓を私たちは深く考えるべきである。「都市を統治すると主張するためには、自らを統治することを学ばなければならない」。この事件まで世論調査で有力視されていたドミニク・ストロス=カーンが、ニューヨークのソフィテルでメイドに対する性的暴行の罪で有罪判決を受けたとしたら、私たちは被害者を哀れむだけでなく、大いに安堵のため息をつくだろう。というのも、フランスでの証言の一部が示唆するように、DSKが強迫的な性犯罪者であり、残虐な行為を犯す可能性があるとすれば、私たちは病的な人物(自制できない場合)か、残忍な人物(自制を拒否する場合)を最高職に選んだことになるからだ。彼の逮捕のニュースが我が国に与えた衝撃を考えると、もし同じ事件が1年後に勃発していたらどうなっていただろうか、と想像する人は少ないでしょう。フランス国民の唖然とした不信感、そして否認に近い感情は、DSKが真摯で責任感のある人物として、世界の舞台で威厳をもってフランスを統治し、代表するだろうという期待に大きく起因しています。この期待は、社会正義と道徳に関する壮大な宣言と、特に金銭に関する個人的な行動との矛盾で厳しく批判されたニコラ・サルコジへの失望から生じています。人々は、より道徳的に模範的な人物を期待していました。裁判の結果がどうであれ、DSKの失脚はなおさら受け入れがたいものです。しかし、政治における美徳の問題を再び公の議論の場に持ち込むというメリットはあります。この問題はアメリカ合衆国では極めて重要ですが、私生活と公的生活、人格と能力を完全に分離する傾向があるフランスでは全く軽視されているからです。正しいアプローチは、この二つの極端な考え方の中間にあると私は考えています。アメリカでは道徳が行き過ぎ、フランスでは政治家個人の道徳観が不十分です。アメリカの「罪探し」の罠に陥ることなく、ソクラテスがアルキビアデスに言ったように、情熱に囚われた人間の良き統治能力は疑わしいということを心に留めておくべきです。最高の責任を果たすには、自制心、思慮深さ、真実と正義への敬意といった美徳を身につける必要があります。こうした基本的な道徳的美徳を自ら身につけていない人間が、都市を統治する際にそれを実践できるでしょうか?最高レベルの政府で誰かが悪行を働かせているのに、どうして皆が良い行いをすることを期待できるでしょうか?2500年前、孔子は済州の君主にこう言いました。「自ら善を求めよ。そうすれば民は善くなる。善人の美徳は風の徳のようなものだ。」 「民衆の美徳は草のようで、風の吹く方向に曲がる」(『会話』12/19)。この言葉は現代の私たちには少し父権主義的に聞こえるかもしれませんが、真実ではないわけではありません。. [...]
ル・モンド・デ・リジョナルズ、第47号、2011年5-6月号 — ここ数ヶ月、アラブ諸国に吹き荒れる自由の風は、西側諸国の政府を不安にさせている。イラン革命のトラウマを抱えた私たちは、何十年も独裁政権を支持し、イスラム主義への防壁だと主張してきた。最も基本的な人権が侵害され、表現の自由が欠如し、民主主義者が投獄され、少数の腐敗したエリート層が国の資源を私腹を肥やすために略奪していることなど、私たちは気にも留めなかった。…私たちは安眠できた。従順な独裁者たちは、制御不能なイスラム主義者による乗っ取りの可能性から私たちを守ってくれたのだ。今日私たちが目にしているのは、これらの人々が立ち上がっているということだ。なぜなら、私たちと同じように、人間の尊厳を支える二つの価値、すなわち正義と自由を切望しているからだ。これらの反乱は、髭を生やしたイデオローグによって起こされたのではなく、絶望に暮れる失業中の若者、教育を受けながらも憤慨する男女、そしてあらゆる階層の市民が、抑圧と不正の終焉を訴えて起こしたのです。彼らは自由に生き、資源がより公平に共有・分配されること、そして正義と独立した報道機関の存在を切望しています。善良な独裁者の鉄拳の下でしか生き残れないと思っていた彼らが、今や私たちに民主主義の模範的な教訓を与えています。混乱や暴力的な弾圧によって自由の炎が消え去らないことを祈りましょう。そして、2世紀前に私たちも同じ理由で革命を起こしたことを、どうして忘れられるでしょうか?政治的イスラムは確かに毒です。エジプトのコプト教徒の暗殺から、冒涜法の改正を支持したパキスタンのパンジャブ州知事の暗殺に至るまで、彼らは神の名の下に容赦なく恐怖を撒き散らしており、私たちはこの悪の蔓延に全力を尽くして対抗しなければなりません。しかし、冷酷な独裁政権を支持することでこれを止めることは決してできません。むしろその逆です。イスラム主義が西洋への憎悪を糧にしていることは周知の事実です。そして、この憎悪の多くは、まさに私たちが現実政治の名の下に常に用いてきた二重基準、すなわち、偉大な民主主義の原則には賛成する一方で、イスラム諸国をより良く統制するためにそれらを適用することには反対する、という二重基準に起因しています。イスラム主義者による政権奪取への懸念は、私にとってますます現実味を帯びてきています。チュニジア、エジプト、アルジェリアにおける現在の蜂起の先鋒たちがイスラム主義者の勢力圏から遠く離れているだけでなく、たとえイスラム主義政党が今後の民主化プロセスにおいて重要な役割を果たすことになったとしても、過半数を獲得できる可能性は極めて低いからです。たとえ1990年代半ばのトルコのように、そうしたとしても、国民がシャリーア法の適用と選挙による監視の免除を認める保証はありません。長年の独裁政権からの脱却を目指す人々は、長年願い、苦労して勝ち取った自由を奪おうとする新たな独裁者の支配に再び屈する望みはほとんどありません。アラブ諸国民はイランの経験を綿密に観察し、アヤトラとムッラーが社会全体に及ぼす圧制を熟知しています。イランの人々が神権政治という残酷な実験からの脱出を模索している今、隣国がそのようなことを夢見る可能性は低いでしょう。だからこそ、私たちは恐怖や些細な政治的思惑を脇に置き、独裁者に立ち向かう人々を熱烈に、そして心から支援しようではありませんか。 [...]
『ル・モンド・デ・リジョニズム』第44号、2010年11-12月号 — ザビエ・ボーヴォワ監督作品『神と人』の大ヒットに、私は深い喜びで満たされています。この熱狂ぶりは実に驚くべきもので、なぜこの映画が私を感動させ、そしてなぜこれほど多くの観客を感動させたのか、ここで説明したいと思います。まず第一に、その抑制されたテンポとゆったりとしたテンポにあります。壮大な演説はなく、音楽も控えめで、予告編のように素早く交互に切り替わるショットではなく、カメラが顔や身振りにじっくりと寄り添う長回しです。すべてが速すぎる慌ただしく騒がしい現代社会において、この映画は私たちを2時間にわたり、内省へと導く異質な時間へと浸らせてくれます。そう感じない人もいれば、少し退屈に感じる人もいるでしょう。しかし、ほとんどの観客は、深く豊かな心の旅を体験するでしょう。なぜなら、素晴らしい俳優陣によって演じられるティビリンの修道士たちは、私たちを彼らの信仰と疑念へと引き込んでくれるからです。そして、これこそがこの映画の二つ目の大きな強みです。二元論的なアプローチとは一線を画し、修道士たちの逡巡、彼らの強さと弱さを描き出しています。驚異的なリアリズムで撮影し、修道士アンリ・カンソンの完璧なサポートのもと、ザビエ・ボーヴォワはハリウッドのスーパーヒーローとは正反対の、苦悩と静寂、不安と自信を併せ持ち、いつ殺されるかわからない場所に留まることの賢明さを常に自問自答する男たちの姿を描き出します。私たちとは全く異なる生活を送る修道士たちは、私たちに寄り添います。信者であろうとなかろうと、私たちは彼らの揺るぎない信仰と恐怖に心を打たれ、彼らの疑念を理解し、この地と地元の人々への愛着を感じます。彼らが共に暮らす村人たちへのこの忠誠心、それが最終的に彼らがこの地を去ることを拒み、ひいては悲劇的な最期を迎える主な理由となるでしょう。そして、これが間違いなくこの映画の三つ目の強みなのです。なぜなら、これらのカトリックの修道士たちは、深く愛するイスラム教の国で暮らすことを選び、現地の人々と信頼と友情を育んでいるからです。それは、文明の衝突が決して避けられないものではないことを示しています。人々が互いに知り合い、共に暮らすとき、恐れや偏見は消え去り、互いの信仰を尊重しながら信仰を生きることができるのです。これは、修道士たちが誘拐され、悲劇的な運命へと突き落とされる場面で、映画の最後でランベール・ウィルソンのナレーションで読み上げられる、修道院長クリスチャン・ド・シェルジェ神父の霊的遺言の中で、深く心に刻まれた言葉です。「もしいつか、そして今日かもしれないが、今やアルジェリアに住むすべての外国人を標的にしているように見えるテロの犠牲者になったら、私の共同体、私の教会、私の家族に、私の人生が神とこの国に捧げられたことを忘れないでほしい。」私は長生きしてきたので、悲しいかな、この世に蔓延しているように見える悪、そして私を盲目的に襲うかもしれない悪にさえ、自分が加担していることを自覚しています。時が来たら、正気を取り戻し、神と仲間の人間の許しを請い、同時に、私を傷つけた者を心から許せるような瞬間が訪れますように。これらの修道士たちの物語は、信仰の証であると同時に、人間性への真の教訓でもあります。動画へのリンクを保存 [...]
『ル・モンド・デ・リジョネス』第43号、2010年9-10月号 — キリスト教週刊誌『ラ・ヴィ』編集長ジャン=ピエール・ドニは、最新エッセイ*で、過去数十年にわたり、1968年5月革命を契機に台頭したリバタリアン・カウンターカルチャーが支配的な文化となり、キリスト教が周縁的なカウンターカルチャーとなってきた様子を描いている。その分析は洞察に富み、著者は征服的でも防御的でもない「異議を唱えるキリスト教」を雄弁に説いている。本書を読むと、多くの読者にとって、控えめに言っても挑発的な問いから始まる、いくつかの考察が生まれる。それは、「私たちの世界はかつてキリスト教的だったのだろうか?」という問いである。キリスト教の信仰、象徴、儀式を特徴とする、いわゆる「キリスト教」文化が存在してきたことは否定できない。この文化が私たちの文明に深く浸透し、世俗化した社会でさえ、暦、祝日、建造物、芸術遺産、民衆の表現など、遍在するキリスト教の遺産に染みついていることは否定できない。しかし、歴史家が「キリスト教世界」と呼ぶ、古代末期からルネサンス期にかけてのこの千年にわたる時代、キリスト教とヨーロッパ社会の融合を示す時代は、真にキリスト教的だったと言えるだろうか。熱烈で苦悩に満ちたキリスト教思想家、セーレン・キェルケゴールにとって、「キリスト教世界全体は、人類が立ち直り、キリスト教から脱却しようとする努力に他ならない」。このデンマークの哲学者が的確に強調しているのは、イエスのメッセージは道徳、権力、そして宗教に関して完全に破壊的であるということ、つまり愛と無力さを何よりも優先しているということである。キリスト教徒は、伝統的な宗教思想と慣習の枠組みの中でそれを再構築することで、人間の心にもっと合うように素早く適応させました。この「キリスト教」の誕生、そして4世紀以降、政治権力と融合して信じられないほど歪められたことは、しばしばその根底にあるメッセージと正反対です。教会は、イエスが制定した唯一の秘跡(聖体)を通してイエスの記憶とその臨在を伝え、イエスの言葉を広め、そして何よりもそれを証しすることを使命とする弟子たちの共同体として必要です。しかし、教会法、尊大な礼儀作法、偏狭な道徳主義、ピラミッド型の聖職階級、秘跡の蔓延、異端との血なまぐさい闘争、そしてそれに伴うあらゆる悪行を伴う聖職者による社会への支配の中に、どうして福音のメッセージを見出すことができるでしょうか。キリスト教は大聖堂の崇高な美しさであると同時に、これらすべてでもあるのです。第二バチカン公会議の教父は、キリスト教文明の終焉を認め、「キリスト教世界は死んだ、キリスト教万歳!」と叫びました。死の数年前にこの逸話を私に語ってくれたポール・リクールは、こう付け加えました。「むしろこう言いたい。『キリスト教世界は死んだ、福音万歳!』。なぜなら、真にキリスト教的な社会など存在しなかったからだ。」結局のところ、キリスト教の衰退は、キリストのメッセージが再び聞かれる機会を与えているのではないでしょうか。「新しいぶどう酒を古い革袋に入れることはできない」とイエスは言いました。キリスト教会の深刻な危機は、福音書の生きた信仰の新たなルネサンスの序章なのかもしれません。隣人愛を神の愛のしるしとして掲げる信仰は、現代の価値観の基盤を成す人権を重視する世俗的なヒューマニズムと強い親和性を持っています。そして、ますます非人間化していく世界の物質主義的かつ商業主義的な衝動に対する、強烈な抵抗の力ともなる信仰。こうして、私たちの「キリスト教文明」の廃墟から、キリスト教の新たな顔が生まれる。キリスト教文化や伝統よりも福音に愛着を持つ信者たちは、その新たな顔に郷愁を感じることはないだろう。*『なぜキリスト教はスキャンダルを引き起こすのか』(Seuil, 2010)。http://www.youtube.com/watch?v=fELBzF4iSg4 [...]
『ル・モンド・デ・リジョネス』第42号、2010年7-8月号 — 世界中のあらゆる文化において、占星術の信仰と実践が根強く残っていることは、特に懐疑的な人にとっては驚くべきことです。中国とメソポタミアの最古の文明以来、占星術の信仰が栄えなかった主要な文化圏は存在しません。17世紀以降、西洋では科学的天文学の台頭により衰退したと思われていましたが、近年、二つの形で復活を遂げたようです。一つは民衆的なもの(新聞の星占い)であり、もう一つは洗練された出生図の心理占星術です。エドガー・モーリンは、心理占星術を一種の「新しい学問」と定義しています。古代文明において、天文学と占星術は密接に結びついていました。天空の厳密な観測(天文学)によって、地球上で起こる出来事(占星術)を予測することが可能になったのです。天体現象(日食、惑星の合、彗星)と地上現象(飢饉、戦争、王の死)の相関関係は、まさに占星術の根幹を成すものです。数千年にわたる観測に基づいているとはいえ、占星術は現代的な意味での科学ではありません。その根拠は証明できず、その実践には無数の解釈が許されるからです。したがって、占星術は、マクロコスモス(宇宙)とミクロコスモス(社会、個人)の間には神秘的な相関関係があるという信念に基づく象徴的な知識です。古代において占星術が成功したのは、帝国が高次の秩序である宇宙に依拠して物事を識別し、予測する必要があったためです。空の兆候を解釈することで、神々からの警告を理解することができました。政治的、宗教的な観点から見ると、占星術は何世紀にもわたって進化し、より個人主義的で世俗的な解釈へと向かってきました。紀元初期のローマでは、人々は特定の医療処置やキャリア計画の適性を判断するために占星術師に相談していました。現代の占星術の復興は、象徴的なツールである出生図を通して自己認識を深めることの必要性をより強く示しています。出生図は、個人の性格や運命の大枠を明らかにすると信じられていました。本来の宗教的信仰は捨て去られましたが、運命論は変わりません。なぜなら、個人は天球がその潜在能力を発揮するまさにその瞬間に生まれると考えられているからです。このように宇宙と人類を結びつけるこの普遍的対応の法則は、西洋においてストア哲学(世界魂)、新プラトン主義、そして古代ヘルメス主義にその起源を持つ、主要な宗教と並行する多面的な宗教潮流である、いわゆる秘教のまさに基盤でもあります。宇宙との繋がりを求める現代人の欲求は、ポストモダニティに特徴的な「世界の再魔法化」へのこの願望に寄与しています。 17世紀に天文学と占星術が分離したとき、多くの思想家は占星術の信仰は永遠に消え去り、単なる迷信と化してしまうだろうと確信していました。しかし、これに異論を唱える声が現れました。近代天文学の創始者の一人、ヨハネス・ケプラーです。彼は占星術のチャートを作成し続け、占星術に合理的な説明を求めるのではなく、その実践的な有効性を認めるべきだと主張しました。今日、占星術は西洋で復活を遂げているだけでなく、ほとんどのアジア社会でも実践され続けています。これは、人類と同じくらい古い時代から続く欲求、つまり、予測不可能で一見混沌とした世界に意味と秩序を見出すという欲求を満たしていると言えるでしょう。長年にわたり、当紙のコラムを通して貢献してくださった友人のエマニュエル・ルロワ・ラデュリー氏とミシェル・カゼナーヴ氏に心から感謝申し上げます。二人は、レミ・ブラーグ氏とアレクサンドル・ジョリアン氏にバトンを託すことになり、私たちは二人を心から歓迎いたします。 http://www.youtube.com/watch?v=Yo3UMgqFmDs&feature=player_embedded [...]
『ル・モンド・デ・リジョニズム』第41号、2010年5-6月号 — 幸福の問題は、あらゆる人間存在の根源であるため、人類の偉大な哲学的・宗教的伝統の核心を成しています。21世紀初頭、西洋社会において幸福の問題が再び浮上したのは、人類に幸福をもたらそうとした壮大なイデオロギーや政治的ユートピアの崩壊に端を発しています。純粋で単純な資本主義は、共産主義やナショナリズムと同様に、集団的な意味体系としての成功を逃しました。残されたのは、個々人が幸福な人生を送ろうとする個人的な探求です。だからこそ、古代哲学や東洋哲学への関心が再び高まり、キリスト教世界の福音主義運動のように、一神教においても、来世だけでなく現世の幸福を重視する運動が発展したのです。人類の偉大な賢者や精神的指導者たちがこのコレクションに表現した様々な視点を読むと、文化の多様性を超越した二つの幸福観の間に、絶え間ない緊張関係が存在していることが感じられます。一方では、幸福は安定的で、決定的で、絶対的な状態として追求されます。これは来世に約束された楽園であり、聖なる生活を送ることで、この地上でその楽園を予感することができます。これはまた、仏教やストア派の賢者たちの探求でもあり、この世のあらゆる苦しみを超えた、今ここでの永続的な幸福の獲得を目指します。このような探求の矛盾は、理論的には誰もが達成できるにもかかわらず、ごく少数の人々しか受け入れることができない禁欲主義と、日常の快楽の放棄を要求することです。もう一つの極端な見方は、幸福は偶然で、必然的に一時的なものであり、そしてあらゆる点を考慮すると、むしろ不公平であるということです。なぜなら、幸福は各個人の性格に大きく左右されるからです。ショーペンハウアーが私たちに思い出させてくれるように、アリストテレスに倣えば、幸福とは潜在能力の実現にあり、各人の気質には確かに根本的な不平等があるのです。したがって、幸福は、その語源が示唆するように、運、つまり「幸運」に起因します。そして、ギリシャ語の「エウダイモニア」は、良いダイモンを持つことを意味します。しかし、こうした多様な視点を超えて、あらゆる学派の多くの賢人たちに共鳴する点があり、私も完全に賛同します。それは、幸福とは、まず第一に、自分自身と人生への健全な愛にあるということです。喜びと悲しみを分け与えながら、あるがままに受け入れ、不幸を可能な限り押しのけようと努めながらも、絶対的な幸福という圧倒的な幻想に囚われない人生です。私たちが愛する人生は、モンテーニュが提唱したように、ありのままの自分を受け入れ、愛することから始まります。自分自身との「友情」です。中国の知恵が教えてくれるように、人生は呼吸のように常に変化し、柔軟に向き合わなければなりません。できるだけ幸せになる最良の方法は、人生に「はい」と言うことです。動画を見る:保存 保存 保存 保存 [...]
『ル・モンド・デ・リジョニツ』第40号、2010年3-4月号 ― ベネディクト16世が教皇ピウス12世の列福手続きを継続することを決定したことは、ユダヤ教界とキリスト教界の双方を二分し、広範な論争を巻き起こした。ローマのラビ共同体の代表は、ホロコーストの悲劇に対するピウス12世の「消極的」な姿勢に抗議し、教皇のローマ大シナゴーグ訪問をボイコットした。ベネディクト16世は、修道院に隠匿されていた多くのユダヤ人が最初の犠牲者となったであろうカトリック教徒への報復のリスクを冒さずに、ナチス政権による残虐行為をこれ以上公然と非難することはできないと主張し、前任者を列聖するという決定を改めて正当化した。この主張は完全に正当である。歴史家レオン・ポリアコフは、1951年に『憎悪の祈祷書:第三帝国とユダヤ人』初版で、すでにこの点を強調していた。「戦時中、死の工場がフル稼働していた間、教皇庁が沈黙を守っていたことは痛ましい。しかしながら、地方レベルでの経験が示しているように、民衆の抗議の直後に容赦ない制裁が下される可能性があったことも認めなければならない」。有能な外交官であったピウス12世は、一石二鳥の策を講じようとした。密かにユダヤ人を支援し、ドイツによる北イタリア占領後、数千人のローマ・ユダヤ人の命を直接救った一方で、ホロコーストへの直接的な非難は避けた。ナチス政権との対話を断ち切らず、残虐な反応を防ぐためだった。この姿勢は、責任感があり、合理的で、思慮深く、賢明でさえあると言えるだろう。しかし、それは予言的ではなく、聖人の行動を反映するものでもない。イエスは、愛と真理のメッセージに最後まで忠実であり続けたがゆえに、十字架上で亡くなりました。イエスに続き、使徒ペトロとパウロも、キリストのメッセージを宣べ伝えることを放棄したり、「外交上の理由」で状況に適応させたりしなかったがゆえに、自らの命を捧げました。もし彼らがピウス12世ではなく教皇だったらどうでしょう?ナチス政権に妥協するのではなく、何百万人もの罪のない人々と共に追放され、死ぬことを選んだとは想像しがたいでしょう。このような悲劇的な歴史的状況において、ペトロの後継者に期待されるのは、まさに聖性であり、預言的な意義を持つ行為です。自らの命を捧げ、ヒトラーに「この忌まわしい行為を容認するよりも、ユダヤ人の兄弟と共に死ぬことを選ぶ」と語る教皇です。確かに、報復はカトリック教徒にとって恐ろしいものだったでしょうが、教会は全世界にかつてないほどの力強いメッセージを送ることができたでしょう。初期のキリスト教徒が聖人であったのは、信仰と隣人への愛を自らの命よりも優先させたからです。ピウス12世は敬虔な人物であり、ローマ教皇庁の優れた行政官であり、優れた外交官でもあったため、列聖される。これは、福音の証しよりも政治的影響力の維持に重きを置いた殉教者教会とコンスタンティヌス帝政以降の教会との根本的な違いを如実に示している。 [...]
『ル・モンド・デ・リジョナルズ』第39号、2010年1月~2月号 — ガリレオの非難から4世紀近くが経った今も、科学と宗教をめぐる世論は依然として二極化しているように見える。一方は、聖書の原理主義的解釈を名目に、否定しようのない科学的発見を否定しようとする創造論者の熱狂。他方は、リチャード・ドーキンス(『神は妄想である』ロバート・ラフォント、2008年)など、科学的論証を用いて神の不在を証明しようとする一部の科学者の著作にメディアが注目する傾向。しかし、こうした立場はどちらの陣営においても極めて少数派である。西洋では、大多数の信者が科学の正当性を認めており、科学者の大半は、科学では神の存在あるいは非存在を証明できないと主張している。結局のところ、ガリレオ自身の言葉を借りれば、科学と宗教は根本的に異なる二つの問いを提起し、それらは矛盾し得ないことが認められている。「聖霊の意図は、天国への行き方を教えることであり、天国がどのように存在するかを教えることではない」。18世紀、カントは信仰と理性の区別、そして純粋理性では神の存在という問いに答えることは不可能であることを改めて強調した。19世紀後半に誕生した科学主義は、科学の勝利によって神の死を繰り返し宣言する、正真正銘の「理性の宗教」となった。リチャード・ドーキンスは、その最新の化身の一つである。創造論もまた、ダーウィンの進化論への反動として19世紀後半に出現した。聖書を原理主義的に解釈した創造論は、進化論を受け入れながらも、インテリジェント・デザイン理論を通して科学を通して神の存在を証明しようとする、はるかに穏健な解釈へと引き継がれた。このテーゼはより容易に受け入れられるが、科学的アプローチと宗教的アプローチを混同するという罠に陥ってしまう。知識形態のこの区別――私には哲学的思考の根本原理のように思える――を受け入れるならば、科学と宗教の間に対話は不可能だと主張すべきなのだろうか?さらに広く言えば、科学的ビジョンと人類および世界に対する精神的な概念の間に対話は不可能だと?本号の特集記事は、そのような対話を訴える国際的に著名な科学者たちの声を代弁している。実際、科学と精神性の間の新たな対話を提唱しつつあるのは、宗教関係者というよりもむしろ科学者たちである。これは主に、過去1世紀にわたる科学そのものの進化によるものである。量子力学の理論は、無限に小さな世界(亜原子の世界)の研究から始まり、物質的現実はニュートンから受け継がれた古典物理学のモデルから想像できるよりもはるかに複雑で、深遠で、神秘的であることを示してきた。もう一つの極限、つまり無限大という点においては、宇宙の起源、特にビッグバン理論に関する天体物理学の発見は、多くの科学者が創造原理の不可能性を主張するために依拠していた、永遠かつ静的な宇宙という理論を覆しました。また、生命の進化と意識に関する研究は、それほどではないものの、「すべてを説明する偶然」や「ニューロン人間」といった科学的なビジョンを限定する傾向にあります。本報告書の前半では、科学者たちが事実(過去1世紀における科学の変化)と、それぞれの哲学的見解(科学と精神性がそれぞれの方法を尊重しながら実りある対話を行える理由)を共有しています。さらに、2人のノーベル賞受賞者を含む他の研究者たちが、科学者として、そして信仰者としての自らの証言を提示し、科学と宗教は対立するどころか、むしろ収束する傾向にあると彼らが考える理由を説明しています。この報告書の第三部では、哲学者たちに議論の場を与えている。彼らは、この新たな科学的パラダイム、そして科学と精神性の間の新たな対話、あるいは収束を提唱する研究者たちの言説について、どのように考えているのだろうか。そのような対話の方法論的視点と限界とは一体何だろうか。これらは、無益で感情的な論争、あるいは逆に表面的な比較を超えて、世界と私たち自身をより深く理解するために不可欠と思われる問いと議論である。 [...]
宗教の世界 2009年11-12月号 — 宗教は恐怖を抱かせる。今日、ほとんどの武力紛争には、程度の差こそあれ、宗教的側面が存在している。戦争とは無縁の場合でも、宗教問題をめぐる論争は、西洋諸国において最も激しいものの一つである。確かに、宗教は人々を結びつけるよりも、むしろ分断させる。なぜだろうか?宗教はその起源から、二重の繋がりの次元を有してきた。垂直方向では、人々と、精神、神、絶対者など、私たちが何と呼ぼうと、より高次の原理との間に絆を生み出す。これが神秘的な次元である。水平方向では、目に見えない超越性への共通の信仰によって結束を感じる人々を結びつける。これが政治的な次元である。これは、「宗教」という言葉のラテン語の語源である「結びつける」という意味のreligereによく表れている。人間集団は共通の信念によって結束しており、レジス・ドゥブレが的確に説明したように、これらの信念は不在の存在、目に見えない力に言及するがゆえに、より強固なものとなる。このように、宗教はアイデンティティ形成において重要な側面を帯びる。各個人はこの宗教的側面を通して集団への帰属意識を持ち、それはまた個人のアイデンティティの重要な部分を構成する。すべての個人が同じ信念を共有していれば、すべてはうまくいく。暴力は、一部の個人が共通の規範から逸脱したときに始まる。これは、集団の社会的結束を脅かす「異端者」や「不信心者」に対する永遠の迫害である。もちろん、暴力は共同体の外、異なる信念を持つ他の都市、集団、あるいは国家に対しても行使される。そして、政治権力が宗教権力から分離している場合でも、宗教はアイデンティティを形成する動員力を持つため、政治家によってしばしば利用される。二度の湾岸戦争において、「ユダヤ・キリスト教十字軍」に対するジハードを呼びかけ、不信心者でありながら世俗国家の指導者であったサダム・フセインを私たちは覚えています。イスラエル入植地における私たちの調査は、もう一つの例を示しています。急速にグローバル化し、恐怖と拒絶を煽る世界において、宗教はあらゆる場所でアイデンティティ政治の復活を経験しています。人々は他者を恐れ、自分自身と文化的ルーツに引きこもり、不寛容を生み出しています。しかし、信者には全く異なるアプローチがあります。それは、自らのルーツに忠実でありながら、他者との違いを受け入れ、対話することです。政治家が宗教を好戦的な目的に利用することを拒むことです。他者への敬意、平和、そして異邦人への歓迎という価値観を育む、それぞれの宗教の核となる教義に立ち返ることです。アイデンティティに基づくものではなく、精神的な側面において宗教を体験することです。宗教は、文化や教義の多様性によって分断されるのではなく、精神的・人道的価値観という共通の遺産を活用することで、地球規模で平和をもたらす役割を果たすことができます。私たちはまだこの目標に程遠いですが、多くの個人や団体がその実現に向けて努力しています。このことも忘れてはなりません。ペギーの言葉を借りれば、「すべては神秘主義に始まり、政治に終わる」のですから、信者が、愛、慈悲、そして許しという宗教共通の神秘的基盤の上に、平和な地球規模の政治空間の構築に向けて努力することは不可能ではありません。つまり、兄弟愛に満ちた世界の到来に向けて努力するということです。ですから、宗教は、信者であれ無神論者であれ不可知論者であれ、人道主義者の目標と一致する、このようなプロジェクトにとって、乗り越えられない障害とは思えません。. [...]
ル・モンド・デ・リジョニツ、2009年9-10月号 — フランスはヨーロッパ最大のイスラム教徒人口を抱えています。しかし、パスカルとデカルトの地における過去数十年間のイスラム教の急速な成長は、人々に不安と疑問を投げかけています。極右勢力の空想的なレトリックは言うまでもありません。彼らはこうした不安を利用し、「多数派となる運命にある宗教の圧力」によってフランス社会が激変すると予言しています。より深刻な問題として、いくつかの懸念は全く正当なものです。宗教を私的な領域に押し込める世俗的な伝統と、学校、病院、公共の場に特化した新たな宗教的要請を、どのように調和させることができるのでしょうか。解放された女性という私たちのビジョンと、悪名高いヘッドスカーフ、そして顔全体を覆うベールといった、女性の男性権力への服従を想起させる強いアイデンティティの象徴を持つ宗教の台頭を、どのように調和させることができるのでしょうか。確かに、文化衝突と価値観の衝突は存在しており、それを否定するのは危険です。しかし、疑問を呈したり批判を表明したりすることは、他者やその違いへの恐怖に駆られた防御的な姿勢で偏見を永続させたり、他者を烙印を押したりすることを意味するものではありません。だからこそ、『ル・モンド・デ・レリジョン』紙は、フランスのムスリムとフランスにおけるイスラム問題について、36ページにわたる大特集を組んだのです。この問題は、最初の移民の到来以来2世紀にわたり具体的な現実であり、サラセン人との戦争や有名なポワティエの戦いを通して、12世紀以上にわたり私たちの集合的な想像力の中に根付いてきました。したがって、ムハンマドの宗教(メディアが報じているように「マホメット」ではなく、これがオスマン帝国との闘争から受け継がれた預言者のトルコ語名であることを知らないため)に対する私たちの恐怖、偏見、そして価値判断をより深く理解するためには、この問題を歴史的に考察することが不可欠です。次に、5つの主要かつ非常に多様な(そして互いに排他的ではない)グループに関するレポートを通して、フランス人ムスリムの銀河を探ろうと試みました。1945年以降にフランスで働くようになった元アルジェリア移民、宗教的アイデンティティを重視する若いフランス人ムスリム、ムスリムとしてのアイデンティティを受け入れながらも、まずはそれを批判的思考と啓蒙主義から受け継がれた人道的価値観に委ねようとする人々、宗教としてのイスラム教から距離を置く人々、そして最後に、原理主義運動であるサラフィー主義に属する人々です。こうしたアイデンティティのモザイクは、非常に感情的で政治的にデリケートな問題の極度の複雑さを露呈しており、公的機関は国勢調査において宗教や民族の所属を用いることを拒否しています。国勢調査はフランス人ムスリムとその人数をより深く理解することを可能にするにもかかわらずです。したがって、このシリーズの締めくくりとして、イスラム教とフランス共和国の関係、あるいは「イスラムフォビア」の問題を分析し、より客観的な視点を持つ複数の学者に発言の機会を与えることが有益だと考えました。イスラム教は、信者数でキリスト教に次いで世界第2位の宗教です。また、フランスでも第2位の宗教であり、カトリックには遠く及ばないものの、プロテスタント、ユダヤ教、仏教にははるかに及ばない規模です。この宗教に対する個人の意見はさておき、これは事実です。私たちの社会が直面する最大の課題の一つは、イスラム教をフランスの文化・政治伝統と可能な限り融合させることです。これは、イスラム教徒にとっても非イスラム教徒にとっても、無知、不信、あるいは攻撃的な雰囲気の中では達成できません。 [...]
ル・モンド・デ・リジョナルズ、2009年7-8月号 — 私たちは前例のない規模の経済危機に陥っています。これは、生産と消費の永続的な成長に基づく私たちの発展モデルに疑問を投げかけるものです。「危機」という言葉はギリシャ語で「決断」「判断」を意味し、「決断を下さなければならない」という極めて重要な瞬間を意味します。私たちは今、根本的な選択を迫られる重大な時期を迎えています。さもなければ、状況は悪化の一途を辿るでしょう。おそらく周期的に、しかし確実に。ジャック・アタリとアンドレ・コント=スポンヴィルが、彼らの興味深い対談の中で私たちに思い出させてくれたように、これらの選択は政治的なものでなければなりません。まずは、私たちが今日生きている異常な金融システムの必要な改革と、より効果的で公正な規制から始めるべきです。また、より環境に優しく、社会的に責任ある製品の購入へと需要を向け直すことで、すべての市民にとってより直接的な影響を与えることも可能です。この危機からの永続的な回復は、金融ゲームのルールと私たちの消費習慣を変えるという真摯な決意にかかっています。しかし、これだけでは十分ではないでしょう。変化が必要なのは、消費の絶え間ない増加に基づく私たちのライフスタイルです。産業革命以来、そして特に1960年代以降、私たちは消費を進歩の原動力とする文明社会に生きてきました。これは経済的な原動力であるだけでなく、イデオロギー的な原動力でもあります。進歩とは、より多くを所有することだ、と。私たちの生活のいたるところに溢れる広告は、あらゆる形でこの信念を強めています。最新の車がなくても幸せになれるでしょうか?最新のDVDプレーヤーや携帯電話がなくても幸せになれるでしょうか?各部屋にテレビとコンピューターがなくても幸せになれるでしょうか?このイデオロギーはほとんど疑問視されることがありません。それが可能なら、なぜダメなのか?そして世界中のほとんどの人々は今、物質的な財の所有、蓄積、そして絶え間ない交換を存在の究極の意味とする西洋モデルに目を向けています。このモデルが崩壊し、システムが脱線し、私たちがこの猛烈なペースで無期限に消費し続けることはおそらく不可能であり、地球の資源は限られており、共有が急務であることが明らかになった時、私たちはようやく正しい問いを投げかけることができるのです。経済の意味、貨幣の価値、そして社会の均衡と個人の幸福の真の条件について、私たちは疑問を投げかけることができます。この点において、この危機は肯定的な影響を与え得るし、また与えなければならないと私は信じています。初めてグローバル化した私たちの文明を、貨幣と消費以外の基準で再構築する助けとなるでしょう。この危機は、単に経済的・金融的なものではなく、哲学的、精神的なものでもあります。それは普遍的な問いを提起します。真の進歩とは何なのか?所有という理想を中心に築かれた文明の中で、人間は幸福になり、他者と調和して生きることができるのか?おそらくそうではないでしょう。貨幣や物質的な財の獲得は、たとえ価値あるものであっても、単なる手段に過ぎません。所有欲は、本質的に飽くことを知らないものです。そして、それはフラストレーションと暴力を生み出します。人間は、たとえ隣人から力ずくで奪うことになっても、常に自分が持っていないものを所有したいと願う生き物なのです。しかし、食料、住居、そしてまともな生活水準といった基本的な物質的ニーズが満たされると、人々は満足し、真の人間になるために、「所有」の論理とは異なる論理、すなわち「存在」の論理に踏み込む必要がある。彼らは自分自身を知り、制御し、周囲の世界を理解し、尊重することを学ばなければならない。愛し、他者と共に生き、フラストレーションに対処し、平穏を得て、人生に避けられない苦しみを乗り越え、そして同時に、目を見開いて死ぬ覚悟をしなければならない。なぜなら、存在は事実だが、生きることは芸術だからだ。賢者に問いかけ、自分自身と向き合うことで、芸術は学べるのだ。. [...]
ル・モンド・デ・リジョニツ、2009年5~6月号 ― 強姦され双子を妊娠していた9歳のブラジル人少女の中絶手術を行った母親と医療チームに対し、レシフェ大司教が破門を宣告したことは、カトリック界に激しい怒りを引き起こした。多くの信者、司祭、そして司教たちまでもが、この懲戒処分は行き過ぎで不適切だとして憤慨を表明した。私も強く反発し、この残忍で独断的な非難と、慈悲、他者への思いやり、そして愛を通して法を超えることを説く福音のメッセージとの間の露骨な矛盾を指摘した。最初の感情が収まった今、この事件を再検討することが重要と思われる。さらなる憤りを煽るためではなく、この事件がカトリック教会に突きつける根本的な問題を、客観的な視点から分析しようとするためである。この決定に対する世論の激しい反発を受け、ブラジル司教会議は破門を軽視し、少女の母親は医療チームの影響を受けたと主張して免除しようとした。しかし、司教省長官バティスタ・レ枢機卿は、レシフェ大司教は単に教会法を繰り返しただけだと明確に説明した。この法は、中絶を行った者は自動的に教会との交わりから排除されると規定している。「中絶を斡旋した者は、その効果が生じた場合には、破門される」(教会法1398条)。誰かが正式に破門する必要はない。彼は自らの行為によって破門したのだ。確かに、レシフェ大司教は教会法を声高に持ち出して火に油を注ぎ、世界的な論争を巻き起こすようなことは避けられたでしょう。しかし、それは多くの信者を激怒させた根本的な問題の解決には繋がりません。キリスト教の法は、強姦を破門に値するほど重大な行為とは見なしていないにもかかわらず、強姦された少女の命を救うために中絶を強要する人々を、どうして非難できるのでしょうか?宗教が規則、原則、価値観を持ち、それらを守ろうと努めるのは当然のことです。今回のケースでは、カトリックが他の宗教と同様に中絶に反対していることは理解できます。しかし、この禁止規定を、個々の事例の多様性を無視して、自動的に懲戒処分を規定する不変の法に定めてよいのでしょうか?この点において、カトリック教会は、ローマ法から受け継がれた教会法とその懲戒処分に相当するものを持たない他の宗教やキリスト教宗派とは異なります。彼らは原則として特定の行為を非難しますが、同時に個々の状況に適応する方法も知っており、規範を破ることが時に「より小さな悪」となると考えています。これは、このブラジル人少女のケースに顕著に表れています。ピエール神父はエイズについても同様のことを述べています。貞潔と貞節によって感染リスクと闘う方がよいが、それができない人にとっては、死を媒介するよりもコンドームを使う方がよい、と。そして、フランスの多くの司教が述べたように、教会の司牧者たちはこの「より小さな悪」の神学を日々実践し、個々の事例に適応し、困難に直面している人々に慈悲の心で寄り添っていることを忘れてはなりません。そのため、彼らはしばしば規則を曲げてしまうのです。そうすることで、彼らは福音のメッセージを実践しているに過ぎません。イエスは姦淫そのものを非難しますが、姦淫の現場で捕まった女性を非難しません。律法の熱狂者たちは彼女を石打ちにしようとしますが、イエスははっきりとこう言います。「罪のない者がまず石を投げなさい」(ヨハネによる福音書8章)。創始者のメッセージに忠実であり、一人ひとりの苦しみと複雑さにますます敏感になっている世界において、存在意義を保ちたいと願うキリスト教共同体が、無差別に懲戒処分を適用し続けることができるでしょうか。理想と規範に加えて、個々のケースに適応する必要性も強調すべきではないでしょうか。そして何よりも、愛は律法よりも強いことを証しすべきではないでしょうか。 [...]
ル・モンド・デ・リジョニツ、2009年3-4月号 ― ベネディクト16世が1988年にルフェーブル大司教によって叙階された4人の司教の破門を解除することを決定したことによって引き起こされた危機は、まだ終息には程遠い。教皇が、教会分離主義者の支持基盤への復帰を求める彼らの布教活動に自らの責務を果たしたことを責める者はいない。問題は別のところにある。言うまでもなく、この発表は、彼らのうちの一人、ウィリアムソン司教による忌まわしいホロコースト否定声明の発表と重なっていた。2008年11月以来、事情通の間では周知の事実であったこの過激派の立場を、ローマ教皇庁が教皇に伝えることを適切だと考えなかったという事実は、すでに悪い兆候である。ベネディクト16世が、1月24日に発表された破門解除を、(1月22日に公知となった)発言の即時撤回の条件としなかったこと、そして教皇がこの件について明確な声明を出すまでに1週間もかかったという事実も、懸念すべき点である。教皇が反ユダヤ原理主義者と共謀していたと疑われているわけではない。教皇は2月12日に「教会は反ユダヤ主義を深く、そして揺るぎなく拒絶することに尽力している」と明確に繰り返し述べていた。しかし、教皇の先延ばしは、原理主義者の社会復帰を絶対的で、ほとんど盲目的な優先事項としているという印象を与え、これらの頑固な信者のほとんどが、第二バチカン公会議によって確立された教会とは完全に相容れない見解に依然として囚われているという事実を見ようとしなかった。破門を解除し、聖ピオ十世会に教会内で特別な地位を与えることを目的とした統合プロセスを開始することで、教皇はルフェーブル大司教の最後の弟子たちが最終的に変化し、第二バチカン公会議が提唱した世界への開放性を受け入れるだろうと確信していたに違いありません。伝統主義者たちは全く逆の考えを持っていました。ルフェーブル大司教によって叙階された4人の司教の一人であるティシエ・ド・マレレ司教は、破門解除の数日後、イタリア紙ラ・スタンパのインタビューで次のように宣言しました。「私たちは立場を変えるつもりはありませんが、ローマを改宗させ、つまりバチカンを私たちの立場に近づけるつもりです。」 6ヶ月前、アメリカの雑誌『アンジェラス』の中で、同じ高位聖職者は聖ピオ十世会の最優先事項は「第二バチカン公会議の誤りを拒絶し続けること」であると主張し、フランス、イギリス、ドイツ、オランダに「イスラム共和国」が出現し、ローマではカトリックの終焉、すなわち「ユダヤ教からの組織的な背教」が訪れると予言していた。聖ピオ十世会は今、ローマに対する最善の戦略に関する立場があまりにも大きく分かれているため、内部崩壊の危機に瀕している。確かなことが一つある。これらの宗派主義的過激派のほとんどは、過去40年間、自分たちのアイデンティティと闘争の基盤となってきたもの、すなわち公会議が提唱する世界への開放性、信教の自由、そして他宗教との対話という原則を拒絶することを放棄するつもりはないのだ。教皇は、一方ではいかなる犠牲を払ってでもこれらの狂信者を教会に迎え入れたいと望みながら、同時に他のキリスト教宗派や非キリスト教宗教との対話も追求できるのでしょうか。ヨハネ・パウロ2世は明確な判断を下すための明確なビジョンを持っていました。実際、1986年のアッシジにおける他宗教との会談こそが、ルフェーブル大司教がローマとの関係を断つ決定的なきっかけとなりました。ベネディクト16世は選出以来、原理主義者への扇動的な言動を数多く行い、エキュメニカル対話や諸宗教対話を阻害し続けています。徹底的な世俗主義、エキュメニズム、良心の自由、そして人権を拒絶し、強硬なカトリックの反近代主義精神と完全に決別することを目指した公会議の対話と寛容の精神を支持する司教たちを含む多くのカトリック信者の間に、大きな不安が広がっているのも無理はありません。創刊5周年を記念して、『ル・モンド・デ・レリジョン』は新しい形式でお届けします。これにより、形式(新しいレイアウト、より多くの図版)と内容の両方が進化しています。書誌情報付きのより充実した資料、アンドレ・コント=スポンヴィルの指導による哲学の充実、新しいレイアウト(「歴史」と「精神性」のセクションが「知識」と「経験」のセクションに取って代わられる)、新しいセクション:「宗教間対話」、「…の人生における24時間」、「…の思想を理解するための3つの鍵」、「芸術家と聖なるもの」、レイリ・アンヴァルによる新しい文芸コラム、宗教関連の文化ニュース(映画、演劇、展覧会)に充てられるページの増加などです。. [...]
宗教の世界 2009年1-2月号 — 世界の様々な宗教の間には、想像するほど共通点が少ない。中でも、有名な黄金律は、千通りもの言い回しで表現される。「自分がされたくないことは、他人にもしてはならない」。この原則とは露骨に矛盾するもう一つの原則がある。それは、その古さ、永続性、そしてほぼ普遍性において驚くべきものだ。それは、女性蔑視である。まるで女性が潜在能力を持つ、あるいは失敗した人間であり、男性より明らかに劣っているかのように。この号の資料で提示する歴史的・文献的要素は、この悲惨な観察を裏付けるため、あまりにも雄弁である。なぜそのような蔑視があるのか?心理的な動機が決定的な要因であることは疑いようがない。ミシェル・カズナーヴが精神分析の先駆者たちに倣って私たちに思い出させてくれるように、男性は女性の快楽に嫉妬すると同時に、女性に対する自身の欲望に怯えているのだ。この問題の核心は間違いなくセクシュアリティであり、ベールをかぶった女性にのみ容認するイスラム教の男性は、女性を潜在的な誘惑者としか見ていなかった教父たちと何ら変わりません。ほぼあらゆる文化における女性のこうした抑圧には、社会史的な理由もあります。宗教はこの抑圧に決定的な影響を与えてきました。非常に古くから伝わる「偉大なる女神」崇拝は、女性原理の尊重を物語っています。人類最古の宗教におけるシャーマンは、崇拝する精霊と同様に、男性または女性であり、これは今日まで受け継がれている口承によって証明されています。しかし、数千年前、都市が発達し、最初の王国が樹立されると、社会組織の必要性が明らかになり、政治的および宗教的な行政が出現しました。そして、政府の役割を担ったのは男性でした。宗教的礼拝を司る司祭たちは、急速に神々を男性化し、地上で起きていた事態を反映して、男性神々が天界で権力を掌握しました。一方、一神教は、この多神教モデルを単に再現し、時には増幅させ、唯一の神に男性的な顔を与えることさえしました。数千年にわたる宗教の大きなパラドックスは、しばしば軽蔑されるにもかかわらず、女性が真の心の拠り所となることです。女性は祈り、知識を伝え、他者の苦しみに共感します。今日、現代社会の世俗化とそれが促進した女性の解放により、女性に対する態度は変化しつつあります。残念ながら、カンダハールで通学途中のアフガニスタンの十代の少女15人が最近酸攻撃を受けた事件のような恐ろしい慣習や、パリス大司教の「スカートを履くだけでは十分ではない。頭の中にも物事を考えなければならない」といった時代遅れの発言は、宗教的伝統が最終的に女性を男性と同等と認め、その教義や慣習から長年にわたる女性蔑視の痕跡を消し去るまでには、まだ長い道のりがあることを示している。. [...]
ル・モンド・デ・リジョニツ、2008年11-12月号 ― 回勅「フマネ・ヴィタエ」発布40周年を記念し、ベネディクト16世は、夫婦が出産間隔をあけることを正当化する「深刻な状況」にある場合、「女性の自然な生殖周期を遵守する」という例外を除き、カトリック教会が避妊に反対する立場を改めて強く表明しました。この発言は当然のことながら、教会の道徳的教義と進化する社会規範との乖離を改めて浮き彫りにする批判の嵐を巻き起こしました。しかし、この乖離自体は、私には正当な批判とは思えません。教会は、どんな犠牲を払ってでも自らのメッセージを売り込まなければならないような企業ではありません。教会の言説が社会の進化と歩調を合わせていないという事実は、時代の精神に対する健全な抵抗の兆候ともなり得ます。教皇は道徳の革命を祝福するためにいるのではなく、たとえ信者の一部を失うリスクを冒しても、自らが信じる特定の真理を守るためにいるのです。避妊を非難するこの考え方に対して真に批判できるのは、それを正当化するために用いられた論拠である。ベネディクト16世はこの点を繰り返した。「生殖を阻止することを目的とした行為によって」生命を与える可能性を排除することは、「夫婦愛の奥深い真理を否定する」に等しい。配偶者の愛を生殖と不可分に結びつけることで、教会の教導権は、聖アウグスティヌスに遡る古いカトリックの伝統と一貫性を保っている。聖アウグスティヌスは肉体と肉欲を否定し、究極的には性関係を生殖の観点からのみ捉えていた。この見解によれば、不妊の夫婦は真に愛を経験できるのだろうか?しかし、福音書にはこのような解釈を裏付けるものは何もなく、他のキリスト教の伝統、特に東方キリスト教の伝統は、愛と人間の性について全く異なる見解を示している。したがって、ここには根本的な神学的問題があり、社会規範の変化ではなく、性と夫婦愛に対する極めて疑わしい見解ゆえに、全面的に再考する必要がある。もちろん、貧困層では避妊が貧困の増大と闘う唯一の効果的な手段となる場合が多いため、こうした言説がしばしば劇的な社会的影響を及ぼすことは言うまでもありません。ピエール神父やエマニュエル修道女(お誕生日おめでとうございます!)といった宗教関係者自身も、ヨハネ・パウロ2世に同様の手紙を書いています。1968年以降、多くのカトリック教徒が教会を去ったのは、性革命だけでなく、こうした深遠な理由によるものであることは間違いありません。エチェガライ枢機卿が最近述べたように、「フマネ・ヴィタエ」は当時「静かな分裂」を引き起こしました。教皇の回勅が伝える結婚生活のビジョンに、多くの信者が衝撃を受けたからです。幻滅したこれらのカトリック教徒は、奔放なセクシュアリティを主張する放蕩な夫婦ではなく、互いに愛し合い、子供を持ちたいという願望から切り離された性生活によって、なぜ自分たちの愛の真実が打ち砕かれなければならないのか理解できない信者なのです。極端に過激な少数派を除けば、他のキリスト教宗派、いや、他の宗教は、このような見解を持っていません。なぜカトリック教会は依然として肉体的な快楽をこれほど恐れているのでしょうか?教会が生命という賜物の神聖性を強調するのは理解できます。しかし、真の愛の中で経験される性行為もまた、神聖な体験ではないでしょうか? [...]
ル・モンド・デ・リジョナル、2008年9-10月号 — その名が示す通り、世界人権宣言は普遍性を目指している。つまり、あらゆる特定の文化的配慮を超越する自然的かつ合理的な基盤に基づくことを意図している。すなわち、出生地、性別、宗教に関わらず、すべての人間は身体的完全性の尊重、信念の自由な表明、人間らしい生活、労働、教育、医療を受ける権利を有する。この普遍主義的な目的は、18世紀のヨーロッパ啓蒙主義の中で生まれたが、ここ20年ほど、一部の国々は人権の普遍性について深刻な留保を表明している。これらは主に、植民地化の犠牲となったアジアとアフリカの国々であり、人権の普遍性と植民地主義的立場を同一視している。つまり、西洋は政治的・経済的支配を押し付けた後、世界の他の地域にもその価値観を押し付けようとしているのである。これらの国々は、文化の多様性という概念を根拠に、人権の相対主義を擁護しています。これらの権利は、各国の伝統や文化によって異なります。こうした論理は理解できますが、私たちは騙されてはいけません。それは独裁政権にとって都合が良く、個人に対する伝統的な支配を強いる慣行の永続化を許すことになります。女性器切除、姦通に対する処刑、父親または夫による後見、早期の児童労働、改宗の禁止など、千もの形態にわたる女性支配です。人権の普遍性を否定する人々は、このことをよく理解しています。これらの権利を適用することで、まさに個人が集団から解放されるのです。そして、身体的および道徳的な完全性を尊重されることを望まない人がいるでしょうか?集団の利益は必ずしも個人の利益とは一致せず、ここに文明の根本的な選択が問われているのです。一方で、西側諸国の政府が必ずしも自らの主張を実践していないことを批判するのは、全く正当なことです。民主主義が模範的であれば、人権の正当性は限りなく強まるでしょう。しかし、一例を挙げると、アメリカ軍がイラク人囚人やグアンタナモ収容所の囚人に対して行った扱い(拷問、裁判の欠如、レイプ、屈辱)は、私たちが人権について説く多くの人々の目に、西洋が道徳的信用を完全に失わせる原因となりました。経済的理由だけが重要視されていたにもかかわらず、民主主義のような価値観を守るという名目でイラクに侵攻したとして、当然ながら批判されています。また、過度の個人主義に苦しむ現在の西洋社会も批判の対象となります。共通善の意識は大きく失われ、社会の結束に問題が生じています。しかし、この欠陥と、個人が集団や伝統の権威に完全に従属する社会の欠陥とを比べれば、誰が真に後者を選ぶでしょうか?基本的人権の尊重は、私にとって不可欠な成果であり、その普遍的な範囲は正当であるように思われます。そうなると、伝統、特に宗教的伝統が深く根付いた文化において、これらの権利を調和的に適用する方法を見つけるという課題が生じますが、それは必ずしも容易ではありません。しかし、よく調べてみると、2500年前に孔子によって書かれ、あらゆる人類文明の中心に何らかの形で刻み込まれた有名な黄金律を通してだけでも、あらゆる文化は人権の本質的な基盤を持っていることがわかります。「自分がされたくないことは、他人にもしてはいけない」 [...]
ル・モンド・デ・リジョニツ、2008年7-8月号 ― 北京オリンピックのわずか数ヶ月前に発生した昨年3月のチベット暴動は、チベット問題を再び国際的な注目を集める残酷な事態へと突き落とした。国民の激しい抗議を受け、西側諸国政府は一致して中国政府に対し、ダライ・ラマとの対話再開を求めた。ダライ・ラマは、多くの同胞の意向に反し、もはやチベットの独立ではなく、中国国内における文化的自治を求めているだけである。暫定的な接触は確立されているものの、賢明な観察者なら誰もが、それが成功する可能性は極めて低いと見ている。現中国国家主席の胡錦濤は20年前、チベットの知事を務めていたが、1987年から1989年にかけての暴動を暴力的に鎮圧したため、「ラサの虐殺者」と呼ばれた。この功績により、彼は党内で目覚ましい昇進を遂げたが、同時に、同年にノーベル平和賞を受賞したチベット指導者に対する深い憤りを抱くようになった。ダライ・ラマを悪魔化し、その死を待ちながらチベットで残虐な植民地政策を続けるという中国指導部の政策は、極めて危険である。彼らの主張に反して、昨年3月の暴動は、20年前の暴動と同様に、チベット亡命政府によって引き起こされたのではなく、意見を述べただけで投獄されること、政府機関でチベット語を話すことを禁じられること、宗教活動への数々の妨害、チベット人よりも数が増えている中国人入植者への経済的優遇など、彼らが受けている抑圧にもはや耐えられない若いチベット人によって引き起こされたのである。 1950年の中国人民解放軍によるチベット侵攻以来、この暴力と差別政策は、かつて国家に対して極めて反抗的で、政治的動機に基づく民族主義的感情よりも、共通の言語、文化、宗教というアイデンティティを通してチベットへの帰属意識を培っていたチベット人の間で、民族主義的感情を強めるばかりでした。60年近くにわたる残忍な植民地支配は、この民族主義的感情をさらに強めるばかりで、圧倒的多数のチベット人が祖国の独立回復を望んでいます。ダライ・ラマのような正統かつカリスマ的な人物だけが、彼らにこの正当な主張を放棄させ、中国の国家空間においてチベット文化の自治という形で、両民族が調和的に共存できるような形で北京当局と合意に至るよう説得することができるのです。 3月22日、中国在住の反体制派中国人知識人30名が、海外メディアに勇気ある論説を発表し、ダライ・ラマの悪魔化とチベットへのいかなる大幅譲歩も拒否する姿勢が、中国を永続的な弾圧という劇的な袋小路へと導いていると強調した。この弾圧は、共産党当局から「少数民族」と呼ばれ、人口のわずか3%を占めるにもかかわらず、領土のほぼ50%を占める3大植民地民族(チベット人、ウイグル人、モンゴル人)の反中感情をますます強めるばかりである。北京オリンピックが恥辱のオリンピックではなく、個人と民族の自決の自由をはじめとする人権尊重の価値観を中国当局が世界に向けて開くためのオリンピックとなることを願おう。. [...]
ル・モンド・デ・リジョナルズ、2008年5~6月号 — ここ数ヶ月、フランスにおいて極めてデリケートな問題である共和国と宗教をめぐって、論争が巻き起こっています。周知の通り、フランスは政治と宗教の分離という苦難の道を歩み、その基盤を築き上げてきました。フランス革命から1905年の政教分離法に至るまで、カトリック教徒と共和主義者の激しい闘争は、深い傷跡を残してきました。他の国々では、宗教が近代政治の構築において重要な役割を果たし、権力分立が論争の的となったことは一度もありませんが、フランスの世俗主義は闘争的な世俗主義でした。ニコラ・サルコジ氏が提唱する、闘争的な世俗主義からより平和的な世俗主義へと移行するという考え方には、私は基本的に賛同します。しかし、それは既に現実のものとなっているのではないでしょうか。共和国大統領がキリスト教の遺産の重要性を強調し、宗教が私的領域と公的領域の両方で果たせる肯定的な役割を強調するのは、正しいことです。問題は、彼の発言が行き過ぎたことであり、当然のことながら強い反発を招いた。ローマ(12月20日)では、彼は聖職者と世俗主義国家の象徴である教師を対立させ、価値観の伝達において前者の方が後者よりも優れていると主張した。リヤド宣言(1月14日)はさらに問題である。ニコラ・サルコジ大統領は「危険なのは宗教的感情ではなく、それを政治目的に利用すること」と正しく指摘しているが、彼は驚くべき信仰告白をしている。「すべての人の思考と心の中にいる超越的な神。人類を奴隷化するのではなく、解放する神」。教皇はこれ以上ないほど的確に表現した。世俗主義国家の大統領の発言としては、確かに驚くべきものだ。ニコラ・サルコジという人物に、そのような見解を持つ権利がないわけではない。しかし、公式の場で表明されれば、国家を揺るがし、サルコジ氏の精神的な見解に賛同しないフランス国民全員に衝撃を与え、ひいては憤慨させるだけだ。共和国大統領は職務を遂行するにあたり、宗教に対して中立を保たなければならない。軽蔑も謝罪もすべきではない。アメリカ憲法が我が国と同様に政治権力と宗教権力を正式に分離しているにもかかわらず、アメリカ大統領は演説で神に言及することをためらわないという反論もあるだろう。確かにその通りだが、神への信仰とアメリカ国家の救世主的役割への信仰は、大多数の人々が共有する自明の理であり、一種の市民宗教の基盤を形成している。フランスにおいて、宗教は人々を結びつけるのではなく、分裂させる。周知の通り、地獄への道は善意で舗装されている。共和国と宗教を和解させるという崇高な意図を持つニコラ・サルコジは、不器用さと過剰な熱意によって、望ましい結果とは正反対の結果をもたらす危険を冒している。彼女の同僚であるエマニュエル・ミニョンも、同様にデリケートなカルト問題において同じ過ちを犯しました。少数派宗教団体を烙印を押すという、時に過度に単純化された政策――多くの法律専門家や学者から非難されている政策(私自身も1995年の議会報告書とそれに付随する常軌を逸したリストを強く批判しました)――を打破しようとして、彼女はカルトを「問題ではない」と断言しすぎています。その結果、彼女が正当に批判している人々は、カルト的な深刻な虐待行為があり、決して問題ではないと見なすことは不可能であることを、同じように正当に、皆に思い出させることが容易になっています。宗教問題が政府の最高レベルで、これまでとは違った、抑制のない方法で取り上げられている今、過度に断定的、あるいは不適切な立場によって、この議論が聞き入れられず、逆効果になっているのは、実に残念なことです。. [...]
ル・モンド・デ・リジョナルズ、2008年3-4月号 — レジス・ドゥブレ様、読者の皆様には、このコラムを先にお読みいただくことをお勧めしますが、その中で、あなたは私にとって非常に刺激的な点を指摘してくださっています。たとえあなたがキリスト教に関する私の論点を多少戯画化しているとしても、私たちの視点の違いは十分に認識しています。あなたはキリスト教の集団的かつ政治的な性格を強調するのに対し、私は創始者のメッセージの個人的かつ精神的な性質を主張します。あなたが社会的な絆の基盤に疑問を投げかけていることは、よく理解しています。あなたは政治的著作の中で、社会的な絆は常に何らかの形で「目に見えない」要素、つまり何らかの形の超越性に基づいていることを、説得力を持って示してきました。18世紀まで、ヨーロッパではキリスト教の神がこの超越性でした。その後、神格化された理性と進歩がそれに続き、20世紀には国家崇拝と偉大な政治イデオロギーが台頭しました。こうした世俗宗教が時に悲劇的な失敗を喫した後、個人主義社会において金銭が新たな宗教としての役割を増大させていることについて、私もあなたと同様に懸念を抱いています。しかし、一体何ができるでしょうか?私たちはキリスト教世界、つまり、今日イスラム教に支配されている社会があるように、キリスト教に支配された社会を切望すべきでしょうか?個人の自由と、異なる思想や宗教を持つ権利が犠牲にされた社会への郷愁でしょうか?私が確信しているのは、「キリスト教」の名を冠し、さらに偉大なことを成し遂げたこの社会は、一方では政教分離を唱え、他方では個人の自由と人間の尊厳を主張したイエスの教えに真に忠実ではなかったということです。キリストが社会の絆としての儀式や教義を含むあらゆる宗教を廃止しようとしたと言っているのではありません。しかし、彼のメッセージの本質は、個人の自由、内なる真実、そして絶対的な尊厳を強調することで、個人を集団から解放することにあることを示したかったのです。現代における私たちの最も神聖な価値観、すなわち人権は、このメッセージに大きく根ざしていると言えるでしょう。キリストは、その先駆者である仏陀と同様に、そして他の宗教の創始者とは異なり、政治に深く関心を抱いていません。彼は、長期的には集団意識の変革につながる可能性のある、個人の意識の革命を提唱しています。個人がより公正で、より意識的で、より誠実で、より愛に満ちるようになるからこそ、社会も最終的に進化するのです。イエスは政治革命ではなく、個人の回心を呼びかけました。伝統への服従に基づく宗教的論理に対して、彼は個人責任の論理に反対したのです。確かに、このメッセージはむしろユートピア的であり、私たちは現在、ある種の混沌の中に生きています。集団の神聖な法への服従に基づく古い考え方はもはや機能せず、真の愛と責任の道を歩む個人はほとんどいないのです。しかし、数世紀後に何が起こるかは誰にも分かりません。付け加えておきますが、この個人意識の革命は、大衆が共有する宗教的・政治的信念や、あなたが正しく指摘したようにメッセージの制度化(その必然性)に反するものではありません。しかし、それは彼らに限界を課すかもしれません。それは人間の尊厳を尊重するというものです。私の見解では、これがキリストの教えのすべてであり、宗教を否定するものではなく、愛、自由、そして世俗主義という三つの不可侵の原則の中に宗教を位置づけています。そして、これは今日、信者と非信者を和解させることができる一種の神聖さであるように思われます。. [...]
ル・モンド・デ・リジョネス、2008年1-2月号 — 物語の舞台はサウジアラビア。19歳の既婚女性が幼なじみと会う。幼なじみは写真を渡すために車に誘う。すると突然、7人の男が現れ、彼女たちを拉致する。男は女性を暴行し、繰り返し強姦する。女性は被害届を出す。強姦犯には軽い懲役刑が言い渡されたが、被害者とその友人は、家族以外の異性と2人きりでプライベートな時間を過ごしたとして、裁判所から鞭打ち刑90回を宣告される(この罪はイスラム法シャリーアで「キルワ」と呼ばれる)。若い女性は控訴を決意し、弁護士を雇い、事件を公表する。11月14日、裁判所は彼女の刑罰を鞭打ち刑200回に増刑し、さらに懲役6年を加算した。 11月14日に判決を下したカティーフ高等裁判所の職員は、裁判所が女性の刑期を重くしたのは「メディアを通じて事態を煽り、司法に影響を与えようとした」ためだと説明した。裁判所はまた、女性の弁護士に嫌がらせを行い、事件の処理を妨害し、弁護士資格を剥奪した。ヒューマン・ライツ・ウォッチとアムネスティ・インターナショナルはこの事件を取り上げ、アブドラ国王に介入して裁判所の不当な決定を覆そうとしている。もしかしたら成功するかもしれない。しかし、勇気を出して声を上げ、自らの悲惨な体験を公表した女性が一人いる一方で、レイプ犯を誘惑した、あるいは夫以外の男性と不倫関係を持ったと非難されることを恐れ、告訴をできずにレイプ被害に遭っている女性はどれほどいるだろうか。アフガニスタン、パキスタン、イラン、そしてシャリーア法を厳格に適用する他のイスラム教国と同様に、サウジアラビアの女性たちの状況は耐え難いものである。現在の国際情勢において、NGOや西側諸国政府からのいかなる批判も、政治・宗教当局だけでなく、国民の一部からも容認できない干渉とみなされています。したがって、イスラム諸国における女性の地位が真に改善されるには、これらの国の世論も反応する必要があります。先ほど述べた事例はメディアの注目を集め、サウジアラビアで大きな反響を呼びました。不正義の犠牲となった女性たち、そして彼女たちの苦境に心を痛める男性たちの並外れた勇気によって、事態は変化するでしょう。まず、こうした改革者たちは、伝統を根拠に、コーランとシャリーアの別の解釈や解釈が存在することを示すことができます。そうした解釈や解釈は、女性により重要な地位を与え、家父長制の恣意的な法から女性をより強く保護するものです。これは、2004年にモロッコで行われた家族法の改革でまさに起こったことであり、大きな進歩と言えるでしょう。しかし、この最初の一歩を踏み出せば、イスラム諸国は必然的に、より深刻な課題に直面することになる。それは、男女の平等を一切認めなかった家父長制社会の中で何世紀も前に確立された宗教的概念と法から、女性を真に解放することである。西洋におけるこのごく最近の意識改革を可能にしたのは世俗主義である。イスラム世界における女性の真の解放には、間違いなく、政教分離も必要となるだろう。. [...]
ル・モンド・デ・リジョニッツ、2007年9-10月号 — ローマ教皇がラテン語ミサを復活させる決定を下したことが、教会内部を含む多くの人々からこれほどの批判を招いたことに、私はいささか驚いている。過去2年間、私はベネディクト16世のあらゆる分野における超反動的な政策を頻繁に指摘してきたので、ここで彼を擁護する喜びに抗うことはできない! 教皇がルフェーブル大司教という迷える羊たちを呼び戻そうとしていることは明白である。しかし、彼には日和見主義的な意図は全くない。ラッツィンガー枢機卿は30年以上もの間、第2バチカン公会議の典礼改革の実施に対する不安と、信者たちに(1570年に公布した)ピウス5世から受け継いだ新典礼と旧典礼のどちらかを選択する権利を取り戻したいという希望を繰り返し表明してきたからだ。これは9月14日から実現される。稀に見る措置で信者に真の選択の自由を与えているにもかかわらず、なぜ不満を言うのでしょうか?第二バチカン公会議まで根強く残っていたキリスト教の反ユダヤ主義を物語る反ユダヤ的な表現が古い典礼から取り除かれた今、会衆が背を向けてラテン語で捧げられるピウス5世のミサが、教会にとって大きな後退となるとは到底考えられません。しかし、三つの個人的な経験が、教皇の健全性を確信させてくれます。テゼを訪れたとき、世界中から集まった何千人もの若者たちがラテン語で歌っているのを見て、私は衝撃を受けました。ロジェ兄弟はその時、その理由を説明してくれました。話されている言語の多様性を考慮すると、ラテン語は誰もが使える典礼言語として確立されていたのです。同様の経験が、カルカッタにあるマザー・テレサの愛の宣教者会の礼拝堂で、世界中から集まった多くのボランティアのために捧げられたミサの最中に起こった。ミサはラテン語で行われ、ほぼ全員が典礼に参加できた。そして明らかに、参加者の幼少期の記憶は今も鮮明に残っていた。カトリック教会の普遍的な典礼言語であるラテン語と、母国語でのミサが並んでいる。なぜダメなのか? 最後に、私が約10年前にチベット仏教を信仰するフランス人信者数十名を対象に行った社会学的調査で遭遇した経験を紹介しよう。彼らの何人かから、母国語ではない言語でチベットの儀式が執り行われるからこそ感謝していると聞き、大変驚いた!彼らは、フランス語で行われる日曜ミサは貧弱で神秘性に欠けるが、チベットの慣習には神聖さを感じると話した。チベット語が彼らにとってのラテン語となったのだ。ベネディクト16世が原理主義者だけを教会に呼び戻すわけではないかもしれない(1)。 … 2003年9月に創刊された『ル・モンド・デ・レリジョン』は、創刊4周年を迎えます。雑誌の質は読者の皆様ご自身で判断していただければ幸いです。しかし、財務状況は非常に良好です。2004年の平均発行部数は4万2千部でした。2005年には5万7千部へと急成長を遂げ、2006年には平均6万6千部と力強い成長を続けました。ストラテジー誌によると、『ル・モンド・デ・レリジョン』は2006年にフランスの出版物の中で3番目に高い成長率を記録しました。この機会に、読者の皆様、そして雑誌にご寄稿くださる皆様に感謝申し上げます。また、よりダイナミックになったフォーラムページのデザイン変更についてもお知らせいたします。また、今夏、『ラ・ヴィ・ル・モンド』グループの取締役を退任されたジャン=マリー・コロンバニ氏にも感謝申し上げます。彼がいなければ、『ル・モンド・デ・レリジョン』は存在し得なかったでしょう。彼が私を編集長に迎え入れた際、宗教問題を断固として世俗的な視点から論じる雑誌の存在がいかに重要かを語ってくれました。雑誌がまだ赤字経営だった時でさえ、彼は私たちを常に支え、編集方針の選択において常に完全な自由を与えてくれました。(1) 17ページの討論をご覧ください。. [...]
宗教の世界、2007年11-12月号 — マザー・テレサは神の存在を疑っていました。何十年もの間、彼女は天国は空っぽだと感じていました。この事実は衝撃的でした。彼女が神について絶えず言及していたことを考えると、この事実は驚くべきことのように思われます。しかし、疑いは神を否定することではなく、疑問を抱くことです。そして、信仰は確信ではありません。確信と確信はしばしば混同されます。確信は、議論の余地のない感覚的証拠(この猫は黒い)から、あるいは普遍的な理性的知識(科学の法則)から生まれます。信仰は個人的かつ主観的な確信です。信じる人によっては、漠然とした意見や疑いのない受け継いだもののように感じられるかもしれません。また、多かれ少なかれ強く根深い確信のように感じられるかもしれません。しかし、いずれの場合も、それは感覚的または理性的な確信とはなり得ません。神の存在を決定的に証明できる人は誰もいないのです。信じることは知ることではありません。信じる人も信じない人も、神が存在するかどうかを説明する優れた議論を常に持ち合わせています。しかし、誰も何も証明することはできません。カントが示したように、理性と信仰の秩序は根本的に異なります。無神論と信仰は確信の問題であり、実際、西洋ではますます多くの人々が不可知論者を自認しています。彼らはこの問題に関して明確な確信を持っていないことを認めているのです。信仰は感覚的証拠(神は目に見えない)にも客観的知識にも基づいていないため、必然的に疑念を伴います。そして、逆説的に見えるものの、完全に論理的なのは、この疑念は信仰そのものの強さに比例するということです。神の存在に弱く固執する信者は、疑念に悩まされることが少なく、信仰も疑念も人生を深刻に混乱させることはないでしょう。逆に、強烈で輝かしい信仰の瞬間を経験した信者、あるいはマザー・テレサのように信仰に全生涯を賭けた信者は、やがて神の不在をひどく苦痛に感じるでしょう。疑念は実存的な試練となるでしょう。リジューのテレーズや十字架の聖ヨハネといった偉大な神秘家たちが、魂の「暗夜」について語る際に経験し、描写しているのはまさにこのことです。彼らは、内なる光がすべて消え去り、信者はもはや頼るものがないため、最もむき出しの信仰に陥るのです。十字架の聖ヨハネは、このようにして、神は信者に退却の印象を与えることで、信者の心を試し、愛の完成への道へと彼らをさらに導くのだと説明しています。これは理にかなった神学的説明です。信仰の外にある合理的な観点からすれば、この危機は、信者が自らの信仰の基盤について確信や客観的な知識を得ることは決してできず、必然的に信仰に疑問を抱き始めるという単純な事実によって容易に説明できます。彼らの疑念の強さは、信仰の存在意義に比例するでしょう。確かに、疑いを経験したことがないと主張する、非常に献身的で非常に敬虔な信者、すなわち原理主義者も存在します。さらに悪いことに、彼らは疑いを悪魔的な現象と見なしています。彼らにとって、疑うことは失敗であり、裏切りであり、混沌に陥ることなのです。彼らは信仰を不当に確信の地位にまで高めているため、内面的にも社会的にも、疑うことを自らに禁じています。疑うことの抑圧は、不寛容、儀礼的な衒学主義、教義の硬直性、非信者の悪魔化、そして時に殺人的な暴力へとエスカレートする狂信など、あらゆる緊張関係を生み出します。あらゆる宗教の原理主義者は、信仰の暗部である疑うことを拒否する点で共通しています。しかし、疑うことは信仰の不可欠な帰結です。マザー・テレサは、どれほど苦痛な経験であり、表現することであっても、自身の疑うことを認めました。なぜなら、彼女の信仰は愛によって動かされていたからです。原理主義者は、自らの疑うことを決して歓迎したり認めたりしません。なぜなら、彼らの信仰は恐怖に基づいているからです。そして、恐怖は疑うことを禁じます。追伸:クリスチャン・ボビン氏をこのコラムに迎えることができ、大変嬉しく思います。. [...]
宗教の世界、2007年7-8月号 — 2006年6月6日(666)の不安の後、2007年7月7日(777)の陶酔が訪れました。ギャンブル関連業者はこれらの日付の象徴的な重要性を強調し、ハリウッド映画は黙示録に登場する有名な獣の数字(666)を巧みに利用し、市長たちはこの有名な7月7日に驚くほど多くのプロポーズを受けています。しかし、7という数字を信じる人々の中で、その象徴性を真に理解している人は誰でしょうか?この数字は、当時観測可能だった7つの惑星にちなんで、古代において完全性と完璧さの象徴として定着しました。ヘブライ語聖書においても、この充足感は受け継がれています。7日目に神は6日間の天地創造の後、休息します。中世には、キリスト教神学者たちがこの意味を取り上げ、7という数字は天(3)と地(4)の同盟を現すと強調しました。それ以来、彼らは聖書の中にその存在を探し出し、解釈し始めました。聖霊の七つの賜物、十字架上のキリストの最後の七つの言葉、主の祈りの七つの祈り、黙示録の七つの教会、そして七人の天使、七つのラッパ、七つの封印などです。中世スコラ哲学もまた、あらゆるものをこの完全な数に還元しようとしました。七つの美徳(人間に由来する四つの枢要美徳と神に由来する三つの神学的美徳)、七つの秘跡、七つの大罪、七つの地獄の階層… 近年、多くの同時代人が数字の象徴性に熱狂していますが(『ダ・ヴィンチ・コード』の「謎かけ」の世界的大ヒットや、安っぽいカバラの大西洋横断的成功を思い浮かべるだけで十分でしょう)、しかしながら、数字に意味と一貫性を与えた宗教文化に基づくものではなくなりました。それは往々にして迷信的なアプローチに行き着く。しかしながら、これは、科学主義の勝利以来、現代社会から追放されてきた象徴的思考と再び繋がるという真の必要性を反映しているのではないだろうか。人間の様々な定義の中で、人間は象徴化が可能な唯一の動物と言えるだろう。周囲の世界に、内なる、あるいは目に見えない世界と繋がる、隠された深遠な意味を求める唯一の存在である。「シンボル」という言葉のギリシャ語の語源である*sumbolon*は、複数の断片に分割された物体を指し、それらの再結合は認識の証となる。分裂させる悪魔(diabolon)とは異なり、シンボルは統合し、繋ぐ。それは、目に見えるものと見えないもの、外的なものと内的なものを繋ぎたいという、精神に根ざした欲求に応えるのだ。だからこそ、人類の黎明期から、このシンボルは人間の精神の深淵と宗教的感情(宗教。ラテン語の語源である*religare*は「結びつける」という意味も持つ)の典型的な表れとして現れてきたのだ。先史時代の人間が死者を花のクッションに寝かせた時、花のシンボルは死者と自分を結びつける愛情と結びついていた。死体を胎児の姿勢で東に向けさせた時、胎児の象徴と日の出の象徴は再生と結びつき、来世への信仰、あるいは希望を表現していた。ドイツ・ロマン派に倣い、カール・グスタフ・ユングは現代人の魂は神話とシンボルの欠如によって病んでいることを示した。確かに近代は新たな神話やシンボルを生み出してきた――例えば広告の神話やシンボルなど――が、それらは私たちの精神が持つ意味への深く普遍的な渇望に応えてはいない。過去30年ほど、占星術と秘教の復活、そして『指輪物語』『アルケミスト』『ハリー・ポッター』『ナルニア国物語』といったフィクション作品の世界的成功は、「世界の再魔法化」の必要性を示唆しています。実際、人間は論理だけで世界や人生と繋がることはできません。心、感受性、直感、そして想像力を通しても繋がる必要があります。そうすることで、シンボルは世界と自分自身への入り口となります。ただし、知識と理性的な識別力を得るための努力は最低限にとどめる必要があります。純粋に魔術的な思考に身を委ねることは、かえって想像力の全体主義に囚われ、記号の解釈錯乱に陥る可能性を秘めているからです。. [...]
ル・モンド・デ・リジョニツ、2007年5~6月号 ― 「ジーザス・キャンプ」。これは、アメリカの福音派を描いた衝撃的なドキュメンタリーのタイトルで、4月18日にフランス映画館で公開された。福音派に属する家庭の8歳から12歳の子供たちの「信仰形成」を追う。子供たちは、ブッシュ支持者の宣教師が教える教理問答の授業に出席するが、その宣教師の発言は身の毛もよだつものだった。かわいそうな子供たちは、クラスメイトたちと同じようにハリー・ポッターを読みたがる。しかし、教理問答教師はそれを厳しく禁じ、魔法使いは神の敵であり、「旧約聖書ではハリー・ポッターは死刑に処せられていた」と皮肉を一切込めずに諭す。そしてカメラは、つかの間の喜びの瞬間を捉える。離婚した両親の子供が、隣人に最新作のDVDを父親の家で見ることができて、いたずらっぽく打ち明けるのだ!しかし、架空の魔法使いの犯罪に対する非難は、サマーキャンプで子供たちが受けている洗脳に比べれば取るに足らないものだ。アメリカ保守派のあらゆる思惑が、最悪の悪趣味で露呈される。まるで新しい救世主のように迎えられるブッシュ大統領の切り抜きの訪問、中絶の恐ろしさを思い知らせるための小さなプラスチック製の胎児の配布、種の進化に関するダーウィンの理論への過激な批判…これらすべてが、カーニバル、拍手、そして異言の歌が絶えない雰囲気の中で繰り広げられる。ドキュメンタリーの最後で、あるジャーナリストがカテキスタを子供たちを洗脳していると非難する。彼女はその質問に少しも動揺しない。「ええ」と彼女は答える。「でも、イスラム教徒も子供たちに全く同じことをするんです」。イスラム教は、ブッシュ支持派の福音主義者たちの強迫観念の一つなのだ。映画の最後は印象的なシーンで締めくくられる。10歳くらいの若い宣教師の少女が、路上で黒人の集団に近づき、「死んだらどこに行くと思う?」と尋ねる。その答えに彼女は言葉を失う。「彼女たちは天国に行けると確信しているの…イスラム教徒なのに」と、彼女は若い宣教師の友人に打ち明ける。友人は一瞬ためらいながら、「きっとキリスト教徒だろう」と結論づける。彼女たちは名ばかりの「福音主義者」だ。彼らの宗派主義的なイデオロギー(私たちこそが真の選民だ)と好戦的な姿勢(世界を支配して改宗させる)は、福音のメッセージとは正反対だ。また、罪、特に性的な罪への執着にも嫌悪感を抱かざるを得ない。性行為(婚姻前、婚姻外、同性間)を非難する姿勢の裏には、抑圧された様々な衝動が隠されているに違いないと考えずにはいられない。 3000万人の会員を擁する全米福音派協会のカリスマ的な会長、テッド・ハガード牧師に起きた出来事は、まさにこのことを如実に物語っています。映画の中で、彼が子供たちに説教する場面が描かれています。しかし、スキャンダルが後から起こったため、映画では触れられていません。同性愛撲滅の闘いの闘士であるハガード牧師が、数ヶ月前、デンバーの売春婦から、常連客で異常な客だと非難されたのです。当初は疑惑を否定していたハガード牧師でしたが、ついに自らの同性愛を認め、長年「この汚物」の犠牲者であったと主張し、信徒に宛てた長文の辞任理由書簡の中で認めました。欺瞞に満ち、偽善的なアメリカ、ブッシュ政権下のアメリカは恐ろしいものです。しかし、私たちは不都合な一般化を避けなければなりません。偏狭な確信と恐ろしいほどの不寛容に囚われたこれらのキリスト教原理主義者たちは、まさにアフガニスタンのタリバンの鏡像と言えるでしょう。しかし、彼らは約5000万人のアメリカの福音派信者の全てを代表するわけではありません。彼らは、イラク戦争に大部分が反対していたことを忘れてはなりません。また、これらの熱狂的な宗教信者たちを、フランスに1世紀以上前から拠点を置き、現在では1850の礼拝所に35万人以上が所属するフランスの福音派信者と同一視すべきではありません。アメリカのメガチャーチに触発された彼らの熱狂的な布教活動は、時に不安を掻き立てます。しかし、過去10年間、公的機関があまりにも安易に行ってきたように、だからといって彼らを危険な宗派と同一視する理由にはなりません。しかし、このドキュメンタリーは、「真実を握っている」という確信が、たとえ善意からであっても、人々を憎悪に満ちた宗派主義へと瞬く間に堕落させてしまう可能性があることを私たちに示しています。. [...]
ル・モンド・デ・リジョニツ、2007年3-4月号 — 前号に掲載したフランスのカトリック教徒に関するCSA世論調査は、200以上のメディアに取り上げられ、論評され、大きな反響を呼び、フランス国内外で多くの反響を呼びました。バチカンでさえ、プパール枢機卿を代表して反応を示し、フランス人の「宗教的無知」を非難しました。これらの反応のいくつかを改めて考察したいと思います。カトリック教徒は、フランスでカトリック教徒であると自認する人の数が劇的に減少した(最新の世論調査では63%だったのに対し、51%に減少)主な原因は、「もしあなたが宗教を持っているとしたら、あなたの宗教は何ですか?」という質問の文言が、より一般的に使われている「あなたはどの宗教に属していますか?」という質問の文言に取って代わったことにあると正しく指摘しました。後者の文言は、社会学的な帰属意識、つまり「私は洗礼を受けたからカトリック教徒です」といった感覚に訴えるものです。私たちが採用した表現は、個人の信仰を測る上ではるかに適切であると同時に、「無宗教」と宣言する可能性もより残しているように思われました。この調査の発表以来、私が繰り返し強調してきたように、洗礼を受けたカトリック教徒は、カトリック教徒であると自認する人よりも多く存在することは明らかです。より伝統的な形式での調査では、おそらく異なる数値が得られるでしょう。しかし、どちらを知ることがより重要でしょうか?カトリック教徒として育てられた人の数でしょうか、それとも現在、自らをカトリック教徒であると考えている人の数でしょうか?質問の仕方だけが結果に影響を与える要因ではありません。アンリ・タンクは、1994年にCSA研究所がル・モンド紙に掲載した調査で、2007年にル・モンド・デ・レリジョン紙に掲載された調査と全く同じ質問をしたことを指摘しています。当時、フランス人の67%がカトリック教徒であると自認しており、12年間で顕著な減少が見られたことを示しています。多くのカトリック教徒――聖職者も信徒も――は、一連の統計が示すように、フランスにおける信仰の衰退に落胆しています。カトリック教徒を自認する人々の中で、真に信仰に身を捧げているのはごく少数です。この調査結果を、親しい友人であった二人の偉大な信者、ドミニコ会のマリー=ドミニク・フィリップとピエール神父(1)の最近の逝去と照らし合わせずにはいられません。全く異なる背景を持つこの二人のカトリックの指導者は、本質的に同じことを私に語ってくれました。数世紀にわたるカトリックの支配的宗教としての崩壊は、福音のメッセージにとって真の機会となり得るのです。福音のメッセージは、より真実で、より個人的で、より生き生きとした方法で再発見される可能性があるのです。ピエール神父の目には、キリスト教のメッセージの力に反する行動をとる、熱意のない大勢の信者よりも、少数の「信じられる信者」の方が望ましいと映ったのです。フィリップ神父は、教会はキリストに倣い、復活祭の日曜日の激動を経験する前に、聖金曜日の受難と聖土曜日の静かな哀悼を乗り越えなければならないと信じていました。敬虔な信者たちは、信仰の衰退に打ちひしがれることはありませんでした。むしろ、彼らはそこに、偉大な刷新の芽、つまり17世紀以上にわたる信仰と政治の混同に終止符を打つ、大きな精神的出来事の可能性を見出しました。この混同は、イエスの「これが私の新しい戒めである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい」というメッセージを歪めてきました。神学者ウルス・フォン・バルタザールが言ったように、「愛だけが信仰に値する」のです。これはピエール神父の驚異的な人気を説明するものであり、フランス人がたとえ自らをカトリック教徒だとは考えていなくても、福音書の根本的なメッセージに対して並外れた感受性を持ち続けていることを示しています。. [...]
『ル・モンド・デ・リジョネス』2007年1-2月号 ― 「フランス、教会の長女」。1896年にランジェニュー枢機卿が述べたこの言葉は、2世紀にキリスト教が伝来し、9世紀以降、カトリックの信仰、象徴、典礼暦を中心に人々が調和して生きるというモデルを示した国の歴史的現実を指し示しています。歴史家たちはこれを「キリスト教国」と呼んでいます。フランス革命、そして1905年の政教分離により、フランスは世俗主義の国となり、宗教は私的な領域へと追いやられました。農村からの人口流出、社会規範の変化、個人主義の台頭など、様々な理由から、カトリックはそれ以来、社会における影響力を着実に失っていきました。この急激な衰退は、フランス教会の統計に最初に顕著に表れており、洗礼数、結婚数、司祭数の着実な減少を示しています(43-44ページ参照)。それは世論調査にも顕著に表れており、世論調査では、実践(ミサへの出席)、信仰(神への)、そして所属(カトリック教徒としての自認)という3つの指標が強調されています。過去40年間、宗教性の最も重要な指標である定期的なミサへの出席は劇的に減少し、2006年にはフランス人口のわずか10%に影響を及ぼしました。神への信仰は1960年代後半まで比較的安定していましたが(約75%)、2006年には52%に低下しました。宗教的側面と文化的側面の両方を包含する所属は、最も重要度の低い指標であり、1990年代初頭まで非常に高い水準を維持していました(約80%)。しかし、過去15年間で劇的な減少が見られ、2000年には69%、2005年には61%にまで落ち込み、私たちの調査では現在51%となっています。この結果に驚き、CSA研究所に18歳以上の全国代表サンプル2,012名による調査の再実施を依頼しました。結果は同じでした。この減少は、回答者の5%が世論調査機関が提示した宗教リスト(カトリック、プロテスタント、正教会、ユダヤ教、イスラム教、仏教、無宗教など)への記載を拒否し、自発的に「キリスト教徒」と回答したことが一因です。通常はこの割合を「カトリック」のカテゴリーに強制的に含めるのに対し、今回は別枠で記載しました。カトリック教徒出身の人々が、キリスト教徒であると自認しながらも、この信仰を否定していることは、私たちにとって重要な意味を持つと考えられます。いずれにせよ、フランスではカトリック教徒であると自認する人がますます少なくなり、「無宗教」と自認する人(31%)が増加しています。その他の宗教はごく少数派で、比較的安定しています(イスラム教4%、プロテスタント3%、ユダヤ教1%)。フランス人の51%がカトリック教徒であると自認する調査(23~28ページ参照)もまた非常に有益であり、信者がいかに教義からかけ離れているかを明らかにしている。カトリック教徒の2人に1人は神の存在を信じていないか、あるいは疑っていないだけでなく、神を信じている人の中でも人格神(これはキリスト教の基盤の一つではあるが)を信じているのはわずか18%で、79%は力やエネルギーを信じている。道徳や規律に関する問題となると、教会との距離はさらに大きくなり、81%が司祭の結婚を支持し、79%が女性の叙階を支持している。そして、カトリックを唯一の真の宗教と考える人はわずか7%である。したがって、教会の教えは信者に対する権威をほぼ失っている。しかし、76%が教会に好意的な意見を持ち、71%が教皇ベネディクト16世に好意的な意見を持っている。この非常に興味深い逆説は、フランスのカトリック教徒が人口の中で少数派になりつつあり、そして確かに既に自らを少数派と認識しているにもかかわらず、深く世俗化した現代社会の支配的な価値観を受け入れていることを示しています。しかし、他の少数派と同様に、彼らは依然として自分たちの共同体のアイデンティティである教会とその主要な象徴である教皇に執着しています。はっきりさせておきましょう。フランスはもはやカトリックの国ではありません。フランスは世俗的な国であり、カトリックは今もなお、そして間違いなく今後も長きにわたって最も重要な宗教であり続けるでしょう。一つの数字を挙げると、私たちが「縮む皮膚」と認識している、定期的に信仰を実践するカトリック教徒の数は、フランスのユダヤ教徒、プロテスタント、イスラム教徒(無神論者と非信仰者を含む)の総数に匹敵します。. [...]
宗教の世界 2006年11-12月号 — ムハンマド風刺画をめぐる論争以来、西洋とイスラム教、あるいはむしろ西洋世界の一部とイスラム世界の一部との間に緊張の兆候が高まっています。しかし、この一連の危機は、イスラム教を批判することは本当に可能なのかという疑問を提起しています。過激派の狂信者だけでなく、多くのイスラム指導者は、信仰を尊重するという名目で、宗教批判を国際法で禁止することを望んでいます。宗教がすべてを包含し、神聖なものが至高の価値とされる社会においては、こうした姿勢は理解できます。しかし、西洋社会は既に世俗化しており、宗教の領域と政治の領域は明確に分離されています。こうした枠組みの中で、国家はすべての市民の良心と表現の自由を保証しています。したがって、誰もが政党や宗教を批判する自由があります。この原則こそが、私たちの民主主義社会が自由社会であり続けることを可能にしているのです。だからこそ、私はロバート・レデカー氏のイスラム教に対する発言には同意できないものの、彼の発言権のために闘うつもりであり、彼が受けた知的テロと殺害脅迫を可能な限り強く非難する。ベネディクト16世の主張とは反対に、キリスト教が暴力を放棄できたのは、ギリシャ理性との特権的な関係や、創始者の平和的な言説によるものでさえなかった。キリスト教が何世紀にもわたって――トマス主義的合理神学の黄金時代を含め――行ってきた暴力は、世俗国家が樹立された時にようやく終結した。したがって、多元主義と個人の自由という近代的価値観を統合しようとするイスラム教にとって、世俗主義とこうしたゲームのルールを受け入れる以外に道はない。前回のコーランに関する報告書で述べたように、これはテキストの出典と伝統法の批判的な再読を意味し、多くのイスラム知識人がまさにそうしている。世俗主義と表現の自由については、私たちは明確な見解を示さなければならない。原理主義者の脅迫に屈することは、自由と世俗主義の世界で生きることを切望する世界中のすべてのイスラム教徒の希望と努力を損なうことにもなります。とはいえ、私は断固として、イスラム教について責任ある態度を取り、理性的に語らなければならないと確信しています。現状では、侮辱、挑発、不正確な発言は、発言者を喜ばせるだけで、穏健派イスラム教徒の任務をさらに困難にしているだけです。イスラム教に対して、単純で根拠のない批判や激しい非難を浴びせれば、過激派からさらに激しい反応を招きかねません。そして、「ほら、私が正しかった」と結論づけるかもしれません。しかし、このように反応する狂信者3人につき、平和的に信仰を実践している、あるいは単に故郷の文化に愛着を持っているイスラム教徒が97人います。彼らは、こうした発言と、過激派の反応によって二重に傷ついており、過激派は自らの宗教の悲惨なイメージを描き出しています。イスラム教の近代化を促進するには、批判的で理性的、そして敬意ある対話こそが、非難や風刺的な発言よりも百倍効果的です。付け加えると、混同は同様に有害です。イスラム教の源泉は多様であり、コーラン自体も多面性を持ち、歴史を通して無数の解釈がなされてきました。そして現代のイスラム教徒も、イスラム教との関係において同様に多様です。ですから、単純化した一般化は避けましょう。私たちの世界は一つの村のようになっています。私たちは、違いを受け入れながら共に生きることを学ばなければなりません。双方が、今流行りの壁を築くことではなく、橋を架けることを目指して話し合いましょう。. [...]
ル・モンド・デ・リジョニズム、2006年9-10月号 ― 『ユダの福音書』は夏の国際的なベストセラーとなった(1)。17世紀もの忘却の末、砂の中から発掘されたこのコプト語のパピルスにとって、これは異例の運命だった。その存在は、これまで聖イレネオの『異端反駁』(180)によってのみ知られていた。それゆえ、これは重要な考古学的発見である(2)。しかし、イエスの生涯の最期については何ら明らかにしておらず、出版社が裏表紙で謳っているように、この小冊子が「教会を刺激する」可能性は低い。第一に、2世紀半ばに書かれたこの文書の著者はユダではなく、物語に意味と権威を与えるためにキリストの使徒に帰したグノーシス派の集団であるからだ(古代では一般的な慣習である)。第二に、1945年のナグ・ハマディの発見により、数多くの外典福音書を含む真のグノーシス主義の蔵書が発掘され、キリスト教グノーシス主義への理解が飛躍的に深まったため、結局のところ、『ユダの福音書』はこの秘教運動の思想に新たな光を当てるものではない。全世界での版権を購入したナショナルジオグラフィック社が完璧に演出した本書の華々しい成功は、間違いなくその異例のタイトル「ユダの福音書」によるところが大きい。衝撃的で、考えられない、破壊的な言葉の組み合わせだ。四福音書とキリスト教の伝統において2000年にわたり「裏切り者」「邪悪な者」「サタンの手先」として描かれ、イエスを一握りの銀貨で売った人物が、福音書を書いたという発想は、実に興味深い。彼が自らに降りかかった汚名を払拭しようと、自らの解釈で事件を語りたかったという事実もまた、素晴らしく説得力のあるものです。そして、この失われた福音書が何世紀にもわたる忘却の後に再発見されたという事実も同様です。つまり、この小さな本の内容を何も知らなくても、このタイトルに魅了されずにはいられないのです。『ダ・ヴィンチ・コード』の成功が如実に示したように、現代社会がキリスト教の起源に関する宗教機関の公式見解に疑問を抱き、ユダの姿がカトリック教会の犠牲者や敗北した敵たちの長いリストと同様に、現代美術や文学によって再評価されていることを考えると、これはなおさら真実です。ユダは現代の英雄であり、感動的で誠実な男であり、失望した友であり、最終的には神の意志の道具となりました。なぜなら、この不運な男に裏切られなければ、キリストはどのようにして普遍的な救済の業を成し遂げることができたでしょうか。ユダに帰せられる福音書は、イエスがユダこそが使徒の中で最も偉大な者であり、自らの死を許す者であることを明言することで、このパラドックスを解決しようと試みている。「しかし、あなたは彼らすべてに勝る!あなたは私の肉体の器である人間を犠牲にするのだ」(56)。この言葉はグノーシス主義の思想を的確に要約している。すなわち、世界、物質、そして肉体は邪悪な神(ユダヤ人と旧約聖書の神)の創造物であり、霊的生活の目的は、秘密の秘儀参入を通して、善にして不可知なる神から発せられる不滅の神聖な魂を持つ、稀有な選ばれた者たちが、肉体という牢獄から魂を解放することにある。寛容を重んじ、唯物主義的で、キリスト教の肉体への軽蔑を批判する現代人が、当時教会当局から宗派主義と物質宇宙および肉体を忌まわしいものとみなしたために非難された学派のテキストにこれほどまでに魅了されていることは、実に興味深い。1. 『ユダの福音書』、R. カッサー、M. マイヤー、G. ヴルスト訳・解説、フラマリオン社、2006年、221ページ、15ユーロ。2. 『ル・モンド・デ・レリジョン』第18号参照。. [...]
宗教の世界 2006年7-8月号 — 仏教が西洋で人気を博している主な理由の一つは、ダライ・ラマのカリスマ的な個性と、寛容、非暴力、慈悲といった根本的な価値観に焦点を当てた教えにあります。この教えが人々を魅了するのは、一神教には滅多に見られない、布教活動的な要素が欠けているからです。「改宗するな、自分の宗教にとどまりなさい」とチベットの導師は語ります。これは表面的な教えで、西洋人を誘惑するためのものなのでしょうか?私はよくこの質問をされます。そこで、私が深く感動したある経験をお話しすることで、この問いに答えたいと思います。数年前、インドのダラムサラでのことでした。ダライ・ラマは、ある本の出版のために私と会う約束をしてくれました。1時間にわたる面会です。その前日、ホテルでイギリス人の仏教徒ピーターと、彼の11歳の息子ジャックに会いました。ピーターの妻は数ヶ月前、長い闘病と深い苦しみの末に亡くなりました。ジャックはダライ・ラマにお会いしたいと願っていました。そこでピーターは彼に手紙を書き、祝福を受けるのにちょうど十分な5分間の謁見を実現させました。父と息子は大喜びしました。翌日、私はダライ・ラマにお会いしました。ピーターとジャックは私のすぐ後に迎えられました。私は彼らがすぐにホテルに戻るだろうと思っていましたが、彼らはその日の終わりまで到着せず、すっかり取り乱していました。謁見は2時間続きました。ピーターはその時のことをこう語っています。「まずダライ・ラマに妻の死について話しました。私は涙が溢れました。ダライ・ラマは私を抱きしめ、私が泣いている間ずっとそばにいてくれました。それから息子のそばにいて、息子と話してくれました。それから彼は私の宗教について尋ねました。私はユダヤ人の血筋と、これまで抑え込んできたアウシュビッツへの家族の強制移送について話しました。」私の心の奥底にあった深い傷が再び開き、感情が溢れ、私は再び涙を流しました。ダライ・ラマは私を抱きしめました。私は彼の慈悲の涙を感じました。彼も私と同じように、私と共に泣いていました。私は長い間、彼の腕の中にいました。それから、私は自分の精神的な旅について彼に語りました。ユダヤ教への関心の薄さ、福音書を読む中でイエスを発見したこと、20年前に私の人生の大きな光となったキリスト教への改宗。それから、英国国教会でイエスのメッセージと同じ力強さを見いだせなかったことへの失望、徐々に離れていったこと、生きる助けとなる精神性への深い欲求、そして、ここ数年チベット仏教を実践している仏教との出会いについて。私が話し終えると、ダライ・ラマは沈黙しました。それから秘書の方を向き、チベット語で話しかけました。秘書は立ち去り、イエスのイコンを持って戻ってきました。私は驚愕しました。ダライ・ラマはそれを私に渡し、「仏陀は私の道、イエスはあなたの道」と言いました。私は3度目の涙を流しました。 20年前の改宗当時、イエスに抱いていた愛が、突然よみがえりました。私はキリスト教徒であり続けたのだと悟りました。仏教に瞑想の支えを求めていましたが、心の奥底では、イエスという存在以上に私を感動させるものはありませんでした。ダライ・ラマは2時間も経たないうちに、私を私自身と和解させ、深い傷を癒してくださいました。そして、ジャックがイギリスに来るたびに必ず会うと約束し、去っていきました。この出会いと、父と息子の変わり果てた顔は、決して忘れることはありません。ダライ・ラマの慈悲が空虚な言葉ではなく、キリスト教の聖人たちの慈悲に決して劣るものでないことを、私に教えてくれたのです。『ル・モンド・デ・リジョニツ』2006年7-8月号. [...]
ル・モンド・デ・リジョナル、2006年5-6月号 — 小説の後は映画。5月17日にフランスで公開される『ダ・ヴィンチ・コード』は、ダン・ブラウンの小説が世界的に成功した理由についての憶測を再び呼び起こすことは間違いないだろう。この疑問は、おそらく小説自体よりも興味深い。歴史スリラーのファン(私もその一人だ)はほぼ全員一致で、『ダ・ヴィンチ・コード』は往年の名作ではないと言う。ページをめくる手が止まらない構成で、最初の数ページから読者を惹きつけ、最初の3分の2は、駆け足の文体や登場人物の信憑性や心理的深みの欠如にもかかわらず、楽しく読める。しかし、その後、筋書きは失速し、滑稽な結末で崩壊する。4000万部以上が売れ、多くの読者にこれほどの情熱を抱かせた理由は、文学分析というよりも社会学的な説明が重要だ。この熱狂の鍵は、アメリカ人作家による短い序文にあると常々考えてきました。序文では、この小説がいくつかの実話に基づいていることが明記されています。その中には、オプス・デイの存在(これは周知の事実です)や、1099年にエルサレムに設立されたとされる秘密結社、レオナルド・ダ・ヴィンチが総長を務めたとされる有名なシオン修道会などが含まれています。さらに驚くべきことに、国立図書館に収蔵されている「羊皮紙」が、この有名な修道会の存在を証明していると言われています。小説の全プロットは、このオカルト的な兄弟団を中心に展開します。この兄弟団は、教会が創立以来隠そうとしてきた重大な秘密、つまりイエスとマグダラのマリアの結婚、そして初期教会における女性の中心的役割を握っていたと言われています。この説自体は目新しいものではありません。しかし、ダン・ブラウンは、この説をフェミニストや秘教の領域から引き出し、ほとんど誰も知らない歴史的事実に基づいていると主張するミステリー小説という形で一般大衆に提示することに成功しました。この手法は巧妙だが、欺瞞に満ちている。シオン修道会は1956年、反ユダヤ主義の作り話作家で、自らをメロヴィング朝の王の子孫だと信じるピエール・プランタールによって設立された。国立図書館に収蔵されている有名な「羊皮紙」は、実際にはこのプランタールとその取り巻きによって1960年代後半に書かれた、ごく普通のタイプライターで打たれた文書である。しかしながら、『ダ・ヴィンチ・コード』は、何百万人もの読者、そしておそらく近い将来には視聴者にとっても、真の啓示となるだろう。初期キリスト教における女性の中心的役割と、4世紀に教会が男性の権力を回復するために画策した陰謀を描いている。陰謀論は、いかに忌まわしいものであろうとも――悪名高い『シオン賢者の議定書』を考えてみてください――残念ながら、宗教機関であれ学術機関であれ、公的機関への不信感を募らせる大衆の心に、いまだに響き続けている。しかし、歴史的実証に欠陥があり、陰謀論的な見せかけに疑問が残るとしても、教会の性差別というテーゼは、否定できない事実にも基づいているため、なおさら魅力的である。カトリック教会では男性だけが権力を握っており、パウロとアウグスティヌス以来、性は軽視されてきたのだ。だからこそ、多くのキリスト教徒、しばしば宗教的に反社会的な人々が、ダン・ブラウンの偶像破壊的なテーゼに魅了され、現代の聖杯を求める新たな探求に乗り出したのも無理はない。それは、マグダラのマリアの再発見と、キリスト教における性と女性性の正しい位置づけである。ブラウンのナンセンスを脇に置いておけば、それは結局のところ、美しい探求ではないだろうか。『ル・モンド・デ・リジョニティ』2006年5-6月号より。. [...]
宗教の世界 2006年3-4月号 — 宗教を笑っていいのでしょうか? 常にこの問いに直面する宗教の世界では、私たちは「はい」と答えます。百回繰り返して「はい」と答えます。宗教的信条や行為はユーモアの域を出ません。笑いや批判的な戯画化の域を出ません。だからこそ私たちは、最初からためらうことなく、この雑誌にユーモラスな漫画を掲載することを選びました。最も深刻な違反行為を抑制するための安全策は存在します。人種差別や反ユダヤ主義、憎悪煽動、個人の名誉毀損を非難する法律です。では、法律に抵触しないものはすべて掲載するのが適切なのでしょうか?私はそうは思いません。私たちは、何の考えも喚起しない、ただ宗教的信条を傷つけたり、不当に歪曲したりすることだけを目的とする、あるいは、例えば創始者やその象徴的なシンボルを通して、ある宗教の信者全員を混同するような、愚かで悪意のある漫画の掲載を常に拒否してきました。小児性愛の聖職者を非難する風刺画は掲載したことがあるが、イエスを小児性愛者の捕食者として描いた風刺画は掲載していない。そのメッセージは「すべてのキリスト教徒は潜在的な小児性愛者である」というものだった。同様に、狂信的なイマームやラビを風刺画に描いたことはあるが、ムハンマドを爆弾製造者として、あるいはモーセをパレスチナの子供たちの殺人者として描いた風刺画は決して掲載しない。すべてのイスラム教徒がテロリストであるとか、すべてのユダヤ人が罪のない人々の殺害者であるとか、示唆することは拒否する。新聞編集者は現代の問題を無視することはできないと付け加えておきたい。彼らの道徳的、政治的責任は民主的な法的枠組みを超えるものである。責任を持つということは、単に法律を尊重することだけではない。理解と政治意識の問題でもある。現在の状況でイスラム嫌悪の風刺画を掲載することは、不必要に緊張を煽り、あらゆる種類の過激派の思う壺に陥れることになる。もちろん、暴力的な報復は容認できない。さらに、これらの漫画は問題のどの漫画よりもはるかにイスラム教を戯画化したイメージを描いており、多くのイスラム教徒はこれに深く悲しんでいます。確かに、私たちはもはや宗教批判を禁じる文化の規則に従うことはできません。ほとんどのアラブ諸国でほぼ毎日掲載されている反ユダヤ主義的な漫画の暴力性を忘れることも、容認することもできません。しかし、これらの理由のいずれも、挑発的、攻撃的、あるいは軽蔑的な態度をとる言い訳にはなりません。それは、私たちが誇りを持って自らのものだと主張する文明の根底にある、宗教的であろうと世俗的であろうと、人道主義的価値観を無視することになります。私たちが信じ込まされているのとは反対に、真の分断は西洋とイスラム世界の間ではなく、対立を望み、火に油を注ぐ人々と、逆に、文化の違いを否定したり軽視したりすることなく、批判的で敬意のある対話、つまり建設的で責任ある対話を確立しようと努める人々の間にあるとしたらどうでしょうか。 (ル・モンド・デ・宗教、2006 年 3 月~4 月). [...]
『ル・モンド・デ・レリジョン』2006年1-2月号 — ちょうど1年前の2005年1月に、『ル・モンド・デ・レリジョン』は新装版を創刊しました。この機会に、同誌の編集面と商業面の進化についてお話ししたいと思います。この新装版は実を結び、発行部数は飛躍的に成長しました。2004年(旧版)の平均発行部数は1号あたり3万8000部でしたが、2005年には5万5000部に達し、45%の増加となりました。2004年末の購読者数は2万5000人でしたが、現在は3万人に増えていますね。しかし、何よりも目覚ましい伸びを見せたのは、ニューススタンドでの売上です。2004年の平均13,000部から2005年には25,000部へと飛躍的に伸びました。フランスの報道界は暗い状況にあり、ほとんどの新聞が発行部数を減らしている中で、このような成長はまさに異例と言えるでしょう。『ル・モンド・デ・レリジョン』の成功を支えてくださったすべての購読者と忠実な読者の皆様に、心から感謝申し上げます。しかしながら、まだ60,000部を超えるという存続の瀬戸際にいるため、早急に勝利宣言をすることはできません。ですから、私たちは引き続き皆様の忠誠心と、『ル・モンド・デ・レリジョン』を広めたいという熱意に頼り、この出版物の存続を確かなものにしていきたいと考えています。多くの皆様から励ましのお手紙やご意見をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。皆様からのフィードバックは、雑誌の発展のために参考にさせていただいております。今号では「ニュース」セクションが削除されていることにお気づきでしょう。隔月発行のスケジュールと、発行の約1ヶ月前に締め切りを迎えるという非常に厳しいスケジュールのため、時事問題のスピードに対応していくことができません。そこで、新フォーマットのコンセプトを踏襲し、「ニュース」ページを社説の直後、巻頭に6ページの主要記事を掲載することにいたしました。記事の内容は、歴史解説または社会学的考察となります。これは、より深く掘り下げた長文記事を求める多くの読者の声に応えるものです。この主要記事の後には、インタラクティブなスペースである「フォーラム」セクションが設けられ、読者からの手紙、オドン・ヴァレットへの質問、著名人による反応やコラム、そして様々なアーティストによるユーモラスな漫画(シャベールとヴァルドールは休憩が必要です)など、より多くのスペースが確保されます。その結果、詳細なインタビューは巻末に掲載されることになりました。創刊1周年を迎えるにあたり、この機会を借りて、『ル・モンド・デ・レリジョン』の成長に尽力してくださった皆様に感謝申し上げます。まずはジャン=マリー・コロンバニ氏。同氏なしではこの出版物は存在し得ず、常に私たちに支援と信頼を寄せてくださっています。また、私たちの発展を支え、サポートしてくださったマルゼルブ出版のチームと歴代取締役の皆様、そしてプロモーション活動や店頭販売に尽力してくださったル・モンドの営業チームの皆様にも感謝申し上げます。最後に、『ル・モンド・デ・レリジョン』の小さなチーム、そしてそこに携わるコラムニストやフリーランス・ジャーナリストの皆様にも感謝申し上げます。彼らは皆様に宗教と人類の叡智をより深く理解していただくために、情熱を持って取り組んでいます。. [...]
ル・モンド・デ・リジョナルズ、2005年11-12月号 — このページで私が共著した作品について触れるのは気が進まないが、非常に時事的なテーマに触れ、かなりの情熱をかき立てるであろうピエール神父の最新の著書について一言述べずにはいられない。*ほぼ1年をかけて、私はエマウスの創設者の考察と疑問を集めた。宗教的狂信から聖体や原罪を含む悪の問題まで、幅広いテーマについてである。28章のうち5章は性道徳の問題に充てられている。ヨハネ・パウロ2世とベネディクト16世がこのテーマに関して厳格であったことを考えると、ピエール神父の発言は革命的に思える。しかし、彼の発言を注意深く読むと、エマウスの創設者は非常に冷静であることがわかる。彼は既婚男性の叙階を支持すると表明したが、奉献された独身生活を維持する必要性を強く主張した。彼は同性間の結婚を非難したわけではなかったが、結婚は異性愛者のための社会制度であり続けることを望んだ。イエスは完全な人間であったため、必然的に性欲の力を経験したと信じていたが、福音書にはイエスがそれに屈したかどうかを判断できる記述はどこにもないとも主張した。最後に、多少異なるが同様に繊細な問題として、女性の叙階に反対する決定的な神学的議論は見当たらず、この問題は主に「弱い性」に対する軽蔑を特徴とする今日まで続く態度の進化に起因していると彼は指摘した。ピエール神父の発言はカトリック教会内で波紋を呼ぶことは必至だが、それは現代の道徳的相対主義を免罪する傾向があるからではなく(これは大きな誤解である)、真にタブー視されている性というテーマについての議論を切り開くからである。そして、この議論がローマによって凍結されているからこそ、ピエール神父の指摘と疑問は、ある人にとっては極めて重要であり、ある人にとっては不安を抱かせるものとなっているのである。本書の出版前、ピエール神父が周囲の人々に原稿を分かち合った際、エマウス教会内部でこの議論を目の当たりにしました。熱狂的な人もいれば、不安や批判的な人もいました。私はまた、それぞれの意見に関わらず、創始者の本書を現状のまま出版するという決断を尊重したエマウス教会の様々な指導者たちにも敬意を表したいと思います。ある指導者は、本書で性に関する記述がかなりの割合を占めていること、そしてそれ以上にメディアの報道の仕方を懸念していました。ピエール神父は、性道徳に関するこれらの問題は、実際には福音書の中で非常に小さな位置を占めていると指摘しました。しかし、教会がこれらの問題を非常に重視しているからこそ、彼はこれらの問題に取り組まなければならないと感じたのです。信仰の基盤とは無関係であり、真摯な議論に値する問題に対するバチカンの強硬な姿勢に、多くのキリスト教徒も非キリスト教徒も衝撃を受けたのです。私はエマウス教会の創始者の見解に完全に賛同します。付け加えておきたいのは、この号で取り上げている福音書がこれらの問いに深く触れていないのは、福音書の主目的が個人や集団の道徳を確立することではなく、一人ひとりの心を、人生を変革し、方向転換させる深淵へと開くことにあるからだということです。教義や規範に固執しすぎて、イエスの「慈悲深くあれ」「裁くなかれ」というメッセージを宣べ伝えることさえ怠った教会は、現代人の多くにとって、キリストの人格とメッセージを見出す上で真の障害となってはいないでしょうか。70年間、福音書のメッセージの最も著名な証人として活動してきたピエール神父ほど、今日、この問題に深く関心を寄せるにふさわしい人物はいないでしょう。*ピエール神父、フレデリック・ルノワール共著「わが神よ…なぜ?」キリスト教信仰と人生の意味についての短い瞑想、Plon、2005年10月27日。. [...]
ル・モンド・デ・リジョネス、2005年9-10月号 — 「なぜ21世紀は宗教的なのか」。この新学期号のメイン特集のタイトルは、アンドレ・マルローの言葉とされる有名なフレーズ「21世紀は宗教的になるか、そうでないか」を彷彿とさせます。このフレーズは心に深く響きます。過去20年間、あらゆるメディアで繰り返し取り上げられ、時には「21世紀は精神的になるか、そうでないか」と言い換えられることもあります。私はすでに、この二つの引用を支持する人々の間で白熱した議論を目の当たりにしてきました。しかし、マルローはこの言葉を口にしたことがないのですから、無駄な争いです!彼の著書、自筆メモ、スピーチ、インタビューのいずれにも、このフレーズの痕跡は見当たりません。さらに重要なのは、マルロー自身が1950年代半ばにこの引用が彼の言葉とされ始めた当初から、一貫して否定していたことです。私たちの友人であり同僚でもあるミシェル・カズナーヴをはじめとするマルローと親しい人々が、つい最近、このことを改めて私たちに思い出させてくれました。では、この偉大な作家は一体何を語ったのか。人々が彼にそのような予言を託すに至ったのだろうか。すべては1955年の二つの文章にかかっていたようだ。デンマークの新聞「ダグリガ・ニュヒト」が道徳の宗教的基盤について質問したところ、マルローはこう締めくくった。「50年間、心理学は悪魔を人間に再統合してきた。これは精神分析学の真摯な評価である。人類がかつて経験した最も恐ろしい脅威に直面する次の世紀の課題は、神々を再導入することだろう」。同年3月、雑誌「プルーヴ」は1945年と1946年に掲載されたインタビューの再掲載版を二本掲載し、『人間の運命』の著者に送られた質問票を補足した。このインタビューの最後に、マルローはこう断言した。「世紀末の決定的な問題は宗教問題となるだろう。キリスト教が古代宗教と大きく異なるように、それは私たちが知っている宗教問題とは大きく異なるだろう」。この二つの引用から、あの有名な定式が構築された。誰がそれを作ったのかは不明だが、この定式は非常に曖昧だ。というのも、私たちが目撃している「宗教の復活」、特にアイデンティティに基づく原理主義的な形態における復活は、ド・ゴール将軍の元文化大臣が言及する宗教とは正反対だからだ。この点において、二つ目の引用は極めて明確である。マルローは、過去の宗教問題とは根本的に異なる宗教問題の到来を告げている。彼は他の多くの文章やインタビューの中で、ベルクソンの「魂の補充」のように、20世紀に人類が陥った深淵から人類を引き出すための、大きな精神的出来事を呼びかけている(このテーマについては、クロード・タネリーの優れた小著『マルローの精神的遺産』(アルレア社、2005年)を参照のこと)。不可知論的なマルローにとって、この精神的な出来事は、決して伝統宗教の復活を求めるものではなかった。マルローは、ヴァレリーにとって文明がそうであったように、宗教も死すべき運命にあると信じていた。しかし、彼にとって宗教は、根源的な肯定的な機能を果たし、それはこれからも機能し続けるだろう。それは、「人類が獣から逃れる道を照らすために、一つ一つ灯される松明」である神々を創造するという機能である。マルローが「21世紀の課題は、神々を人類に再び導入することである」と主張するとき、彼は新たな宗教性の高まりを呼びかけている。しかしそれは、精神分析における悪魔のように、人間の精神の奥底から湧き上がり、神性を精神に意識的に統合する方向へと向かうものであり、伝統宗教にしばしば見られたような、神性を外に投影するものではない。言い換えれば、マルローは新たな精神性の到来を待ち望んでいたのです。それは人間性を体現する精神性であり、その精神性は萌芽期にあるかもしれないものの、今世紀初頭においては、伝統的な宗教的アイデンティティの激しい衝突によって依然として大きく抑圧されているものです。追伸1:ジェナーヌ・カレ・タガー氏が『ル・モンド・デ・レリジョン』の編集長に就任することを大変嬉しく思います(彼女は以前は編集秘書を務めていました)。追伸2:読者の皆様に、『ル・モンド・デ・レリジョン』の教育的な特集号の新シリーズ「理解への20の鍵」の創刊をお知らせします。第1号は古代エジプトの宗教に焦点を当てています(7ページ参照)。
[...]
宗教の世界、2005年7-8月号。ハリー・ポッター、『ダ・ヴィンチ・コード』、『指輪物語』、『アルケミスト』。この10年間の文学と映画の大ヒット作には共通点が一つあります。それは、私たちの好奇心を満たしてくれることです。神聖な謎、魔法の呪文、奇妙な現象、そして恐ろしい秘密が散りばめられたこれらの作品は、私たちのミステリーへの渇望、説明のつかないものへの憧憬を満たしてくれます。これはまさに、私たちの超近代化の逆説と言えるでしょう。科学が進歩すればするほど、私たちは夢と神話を必要とします。世界が解読可能で合理化可能に思えるほど、私たちはその魔法のオーラを取り戻そうとするのです。私たちは今、世界を再び魅了しようとする試みを目撃しています…それはまさに、世界が魔法を失ってしまったからです。カール・グスタフ・ユングは半世紀前にこう説明しました。「人間は感情と同じくらい理性、神話と同じくらい科学、シンボルと同じくらい議論を必要とするのです。」なぜでしょうか?それは、人間が単なる理性的な存在ではないからです。私たちはまた、欲望、感受性、心、そして想像力を通して世界と繋がっています。論理的説明と同じくらい夢に、客観的知識と同じくらい詩や伝説に、私たちは養われます。19世紀(啓蒙時代よりも)から受け継がれたヨーロッパ科学主義の誤りは、このことを否定したことでした。人間の非合理的な部分は根絶され、すべてはデカルトの論理で説明できると信じられていました。想像力と直感は軽蔑され、神話は子供のおとぎ話のような地位に追いやられました。キリスト教会は、ある程度、合理主義的な批判に従っていました。彼らは、理性に訴える独断的で規範的な言説を重視し、心と繋がる内的経験、あるいは想像力に訴える象徴的な知識を伝えることを犠牲にしました。こうして、私たちは今日、抑圧されたものの復活を目撃しているのです。ダン・ブラウンの読者は主にキリスト教徒であり、彼らは彼の難解なスリラー作品に、もはや教会では見出せない神秘、神話、そして象徴性を求めています。『指輪物語』のファンは、バーナード・ワーバーの熱心な読者と同様に、科学技術の深い知識を持つ若者が多いですが、同時に、自分たちが宗教から大きく距離を置いているにもかかわらず、宗教とは異なる神話に触発された幻想的な世界を渇望しています。こうした神話と驚異の復活を憂慮すべきでしょうか?それが理性と科学の拒絶につながらない限り、もちろん憂慮する必要はありません。例えば宗教は、道徳的・神学的な教えの深遠さを放棄することなく、感情、神秘、そして象徴性へのこうした欲求をより重視すべきです。 『ダ・ヴィンチ・コード』の読者は、小説の魔法と秘教の偉大な神話(テンプル騎士団の秘密など)に心を動かされるでしょう。著者の主張を額面通りに受け止めたり、全くの虚構の陰謀論の名の下に歴史的知識を否定したりする必要はありません。言い換えれば、すべては欲望と現実、感情と理性の間の適切なバランスを見つけることなのです。人間が真の人間であるためには驚異が必要ですが、夢を現実と取り違えてはいけません。(ル・モンド・デ・リジョネス、2005年7-8月号). [...]
ル・モンド・デ・リジョニズム、2005年5-6月号 — 思想家であり、神秘主義者であり、並外れたカリスマ性を持つ教皇であったカロル・ヴォイティワは、後継者に複雑な遺産を残しました。ヨハネ・パウロ2世は多くの壁を取り壊しましたが、同時に新たな壁を築きました。この長く矛盾に満ちた教皇在位期間は、特に他宗教への開放性と教義および規律の閉鎖性を特徴としており、カトリック教会の歴史、そしておそらくは歴史そのものにおいても最も重要な章の一つとなることは間違いありません。私がこの記事を書いている今、枢機卿たちはヨハネ・パウロ2世の後継者選出の準備を進めています。新教皇が誰であれ、彼は数多くの課題に直面することになるでしょう。これらは、カトリックの未来にとっての主要な課題であり、私たちは特集記事でこの問題を取り上げます。レジス・ドゥブレ、ジャン・ムッタパ、アンリ・タンク、フランソワ・テュアル、オドン・ヴァレらが本稿で提起した分析や数々の論点、あるいは他の宗教やキリスト教宗派の代表者たちの発言については、ここでは改めて取り上げません。ただ一つの側面に注目したいだけです。カトリック教会にとって、他のあらゆる宗教と同様に、主要な課題の一つは、現代人の精神的なニーズに応えることです。これらのニーズは現在、カトリックの伝統とは全く相容れない三つの形で表現されており、ヨハネ・パウロ二世の後継者たちの課題を極めて困難なものにするでしょう。実際、ルネサンス以降、私たちは個人化とグローバル化という二重の潮流を目の当たりにしてきました。そして、この30年間、この潮流は着実に加速しています。宗教の領域における結果として、個人は、象徴、慣習、教義というグローバルな資源から引き出し、個人の精神性を構築する傾向があります。今日の西洋人は、カトリック教徒であることを容易に自認し、イエス・キリストの人格に心を動かされ、時折ミサに出席する一方で、禅の瞑想を実践し、輪廻転生を信じ、スーフィーの神秘主義を信奉する。南米人、アジア人、アフリカ人も同様で、彼らもまた長きにわたりカトリックと伝統宗教の融合に惹かれてきた。こうした「象徴的なブリコラージュ」、つまり「宗教的逸脱」の実践はますます広まりつつあり、カトリック教会が信者たちに、いかにして深く愛着を持つ教義と実践の厳格な遵守を強制できるのか、理解に苦しむ。もう一つの大きな課題は、非合理的で魔術的な思考の復活である。西洋で長きにわたり進行し、キリスト教に深く浸透してきた合理化のプロセスは、今や反動、すなわち想像力と魔術的思考の抑圧を生み出している。しかし、レジス・ドゥブレがここで指摘するように、世界がますます技術的かつ合理化されていくにつれて、その代償として、情緒的なもの、感情的なもの、想像力豊かなもの、そして神話的なものへの需要が高まっていく。だからこそ、秘教、占星術、超常現象、そして歴史的宗教自体における魔術的実践の発展――例えばカトリックとイスラム教における聖人崇拝の復活――が成功を収めているのだ。これら二つの潮流に加えて、カトリックの伝統的な視点を覆す現象が加わる。現代人は来世の幸福よりも、現世の幸福をはるかに重視しているのだ。こうして、キリスト教の司牧的アプローチ全体が変容する。もはや天国と地獄ではなく、感情的な交わりの中でイエスに出会ったことで今まさに救われたと感じる幸福に焦点が当てられている。教導権の一部門は、教義や規範への忠実な遵守よりも、意味と感情を優先するこの進化に、依然として歩調を合わせていない。現世の幸福を目的とした、融合的で魔術的な慣習。これこそが、先史時代の宗教(資料参照)を受け継ぐ古代の異教の特徴であり、教会は自らの地位を確立するために、この宗教と激しく闘いました。超近代化の中で、古風なものが力強く復活を遂げています。これはおそらく、21世紀にキリスト教が直面する最大の課題でしょう。. [...]
ル・モンド・デ・リジョナル、2005年3-4月号 — 悪魔が存在するかどうかは関係ありません。否定できないのは、悪魔が戻ってきているということです。フランスでも世界中でも。派手で劇的な形ではなく、拡散し多面的な形で。多くの兆候が、この驚くべき復活を示しています。墓地の冒涜は、人種差別的というよりは悪魔崇拝的な性質のものが多く、過去10年間で世界中で増加しています。フランスでは、過去5年間でユダヤ教、キリスト教、イスラム教の墓3000基以上が冒涜されたと報告されており、その数は前の10年間の2倍です。フランス人で悪魔の存在を信じているのはわずか18%ですが、この信念を共有する人が最も多く(27%)、そのうち34%は、人は悪魔に取り憑かれる可能性があると考えています(1)。地獄の存在を信じる人は、過去20年間で28歳以下でも倍増しています(2)。私たちの研究によると、ゴスやメタルミュージックといったティーンカルチャーのかなりの部分が、父なる神に敵対する典型的な反逆者、サタンへの言及で満ち溢れています。この病的で時に暴力的な世界を、反抗と挑発への欲求が自然に現れたと解釈すべきでしょうか?それとも、悪魔とその手下たちを描いた映画、コミック、ビデオゲームの急増で説明すべきでしょうか?1960年代と70年代のティーンエイジャー(私もその一人でした)は、消費社会への拒絶を通して、自らの違いや反抗を表現する傾向が強かったのです。ベルゼブブや超暴力的なヘビーメタルよりも、インドのグルやピンク・フロイドの幻想的な音楽の方が私たちを魅了しました。悪へのこの魅了は、伝統的な価値観や社会的な絆の崩壊、そして未来への深い不安に特徴づけられる、現代の暴力と恐怖の反映ではないでしょうか?ジャン・デルモーが指摘するように、歴史は、恐怖が高まった時代にこそ悪魔が再び前面に出てくることを示しています。サタンが政治に舞い戻ったのも、まさにこの理由ではないでしょうか。ホメイニ師が「偉大なるアメリカのサタン」を非難した際に再び導入された悪魔への言及と、政敵の明確な悪魔化は、ロナルド・レーガン、ビン・ラディン、そしてジョージ・ブッシュによっても引き継がれました。さらに、ブッシュは、悪魔祓いの実践を増やし、悪の勢力に支配された世界を非難するアメリカの福音派の間でサタンが著しく人気を取り戻していることに触発されたに過ぎません。西側諸国の世俗化の進展を「サタンの煙」と表現したパウロ6世以来、長らく悪魔から距離を置いてきたカトリック教会も、その流れに遅れをとってはいません。そして、時代の兆しとして、バチカンは名門ローマ教皇庁立レジーナ・アポストロルム大学内に悪魔祓いセミナーを新設した。こうした兆候は、悪魔の復活だけでなく、その正体と役割についても徹底的な調査を迫るものとなった。悪魔とは誰なのか?宗教において悪魔はどのように現れたのか?聖書とコーランは悪魔について何を語っているのか?なぜ一神教は、シャーマニズム、多神教、あるいはアジアの宗教よりも、絶対的な悪を体現するこの人物像をより強く必要とするのだろうか?さらに、精神分析はどのようにしてこの人物像とその精神的機能に光を当て、聖書における悪魔の象徴的再解釈を刺激的なものにすることができるのだろうか?なぜなら、語源によれば、「シンボル」―スムボロン―が「結びつけるもの」であるならば、「悪魔」―ディアボロン―は「分裂するもの」だからである。一つ確かなことがある。それは、私たちが個人的、集団的に抱く恐怖と「分裂」を認識し、それらを意識と象徴化という困難なプロセスを通して明るみに出し、私たちの影の部分を統合することによってのみ――ジュリエット・ビノシュが洞察に満ちたインタビューで私たちに教えてくれたように――私たちは、悪魔と、人類と同じくらい古くから存在する、他者、異なるもの、異質なものに、抑えきれない衝動と分裂への不安を投影するという古風な欲求を克服できるということだ。(1) 2002年12月のソフレ/ペレラン誌の世論調査による。(2) ヨーロッパ人の価値観、フューチュリブルズ、2002年7-8月号
[...]
宗教の世界 2005年1-2月号 — 社説 — 私が1980年代後半に出版とジャーナリズムの仕事を始めた頃、宗教は誰の関心も惹きつけませんでした。今日では、宗教は様々な形でメディアに浸透しています。実際、21世紀は「宗教現象」が世界の出来事や社会の行方に対する影響力を増大させながら幕を開けています。なぜでしょうか?私たちは現在、宗教の二つの全く異なる側面、すなわちアイデンティティの復活と意味への欲求に直面しているからです。アイデンティティの復活は地球全体に影響を及ぼします。それは文化の衝突、そして民族、国家、あるいは文明のアイデンティティの象徴として宗教を動員する新たな政治的・経済的対立から生じています。意味への欲求は、主に世俗化され脱イデオロギー化された西洋社会に影響を与えています。超近代的な人々は宗教機関を信用せず、科学と政治が約束する明るい未来をもはや信じず、自らの人生を設計しようとしています。それでもなお、彼らは起源、苦しみ、そして死という深遠な問いに取り組み続けています。同様に、彼らは儀式、神話、そして象徴を必要としています。この意味への欲求は、人類の偉大な哲学的・宗教的伝統、すなわち仏教と神秘主義の成功、秘教の復興、そしてギリシャの叡智への回帰を再検証するものです。アイデンティティと精神性という二重の側面を持つ宗教の覚醒は、「宗教」という言葉の二重の語源、「集まること」と「つながること」を想起させます。人間は天に目を向け、存在の謎に疑問を抱くことから、宗教的な動物です。彼らは神聖なものを受け取るために集まります。また、超越性に基づく神聖な絆で、他の人間と繋がろうとすることからも、宗教的なのです。宗教のこの垂直と水平の二重の側面は、太古の昔から存在してきました。宗教は、文明の誕生と発展を牽引する主要な原動力の一つでした。宗教は崇高なものを生み出してきました。聖人や神秘主義者の積極的な慈悲、慈善活動、最高傑作、普遍的な道徳観、そして科学の誕生さえも。しかし、より苛酷な形では、常に戦争や虐殺を煽り、正当化してきました。宗教的過激主義にも二つの側面があります。垂直方向の毒は、独断的な狂信、あるいは妄想的な非合理性です。これは一種の確信の病理であり、信仰の名の下に個人や社会をあらゆる極端へと駆り立てます。水平方向の毒は、人種差別的な共同体主義、つまり集団的アイデンティティの病理です。この二つの爆発的な混合が、魔女狩り、異端審問、イツハク・ラビンの暗殺、そして9.11を生み出しました。地球に及ぼす脅威に直面して、一部のヨーロッパの識者や知識人は、宗教を過激な形態に矮小化し、全面的に非難しようとします(例えば、イスラム教=過激イスラム主義)。これは重大な誤りであり、まさに私たちが戦おうとしているものを増幅させるだけです。宗教的過激主義を打ち破るには、宗教の肯定的かつ文明的な価値を認識し、その多様性を受け入れること、人類が個人的にも集団的にも神聖なものと象徴を必要としていることを認めること、そして宗教を政治的に操作することが現在成功している原因となっている諸悪の根源、すなわち南北格差、貧困と不正義、新たなアメリカ帝国主義、過度に急速なグローバリゼーション、そして伝統的なアイデンティティと慣習への軽蔑に取り組むことが必要です。21世紀は私たちがどのように作り上げるかによって決まります。宗教は、多様な文化の中で個人の充足と世界平和を促進する触媒となる可能性もある一方で、征服と破壊の政策に利用される象徴的な道具となる可能性もあるのです。. [...]
ル・モンド・デ・レリジョン、2004年11-12月号 ― 社説 ― ここ何年か、私たちは、アイデンティティ政治の強化と結びついた宗教的確信の復活を目撃しており、それがメディアの注目を集めています。これは氷山の一角に過ぎないと思います。西洋に関しては、この1世紀になされた進歩を見失ってはなりません。フランスの政教分離法施行100周年を記念する特集号は、当時カトリックと反教権派の間に蔓延していた、憎悪と排斥という信じられないほどの状況を改めて掘り下げる機会を与えてくれました。ヨーロッパにおいて、19世紀から20世紀への転換期は、確信によって特徴づけられました。イデオロギー的、宗教的、そして科学的確信です。多くのキリスト教徒は、洗礼を受けていない子供は地獄に行き、自分たちの教会だけが真理を持っていると信じていました。無神論者は宗教を軽蔑し、人類学的(フォイエルバッハ)、知的(コント)、経済的(マルクス)、あるいは心理的(フロイト)な疎外とみなしていました。今日、ヨーロッパとアメリカ合衆国では、最近の調査によると、信者の90%が、単一の宗教が真理を持つのではなく、すべての宗教に真理が存在すると信じています。無神論者もまた寛容になり、ほとんどの科学者はもはや宗教を科学の進歩とともに消滅する運命にある迷信とは考えていません。全体として、わずか1世紀の間に、私たちは確実性の閉ざされた世界から、確率の開かれた世界へと移行しました。フランソワ・フューレが「近代の越えられない地平線」と呼んだこの近代的な懐疑主義は、信者が他の宗教に心を開いただけでなく、近代が進歩という科学神話から受け継いだ確実性を捨て去ったことでも、私たちの社会に広まりました。つまり、知識が進歩するにつれて、宗教と伝統的価値観は後退するのです。では、私たちはモンテーニュの弟子になったのではないだろうか。哲学的あるいは宗教的信念がどのようなものであれ、西洋人の大多数は、人間の知性は究極の真理や決定的な形而上学的確実性に到達できないという仮説を支持している。言い換えれば、神は不確実である。偉大な哲学者が5世紀前に説明したように、人は不確実性の中でしか信じることができず、また信じないこともできない。ここで明確にしておきたいのは、不確実性は疑念を意味するわけではないということだ。人は信仰、深い確信、そして確信を持っていても、他の人々が善意と、自分と同じくらい多くの正当な理由から、それらを共有しないかもしれないことを認めることができる。ル・モンド・デ・レリジョン紙に寄せた二人の演出家、エリック=エマニュエル・シュミットとピーター・ブルックのインタビューは、この点について雄弁に語っている。シュミットは「知識から来ない」「識別不可能な神」を熱烈に信じ、「自らを疑わない思考は知性を持たない」と断言している。後者は神について言及していないものの、「知られざる、名状しがたい」神的存在への扉を開き、「『私は何も信じない…』と言いたかったのですが、何も信じないということは、依然として信念の絶対的な表現なのです」と告白している。こうした発言はこの事実を如実に示している。そして、私見では、ステレオタイプや単純化された言説から脱却するために、この事実についてさらに深く考える価値がある。今日の真の分断は、前世紀と同様に、「信者」と「非信者」の間ではなく、「信者」あるいは「非信者」のうち、不確実性を受け入れる者とそれを拒絶する者との間の分断となっているのだ。—『ル・モンド・デ・レリジョン』2004年11-12月号 [...]
保存