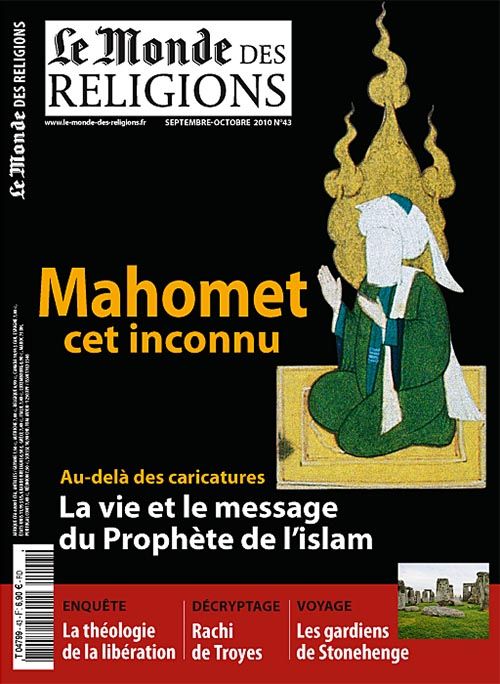 宗教の世界 第43号、2010年9-10月号 —
宗教の世界 第43号、2010年9-10月号 —
『ラ・ヴィ』の編集長、ジャン=ピエール・ドニは、最新エッセイ*の中で、過去数十年にわたり、1968年5月に勃興したリバタリアン・カウンターカルチャーが支配的な文化となり、キリスト教が周縁的なカウンターカルチャーとなってきた様子を描いています。その分析は的確で、著者は「異議を唱えるキリスト教」います。本書を読んで、私は幾度か考えさせられました。まずは、控えめに言っても多くの読者にとって挑発的に思えるであろう問いから始めます。私たちの世界は、かつてキリスト教的だったことがあるのでしょうか?キリスト教の信仰、象徴、儀式を特徴とする、いわゆる「キリスト教」文化が存在したことは明白です。この文化が私たちの文明に深く浸透し、世俗化されてもなお、私たちの社会が遍在するキリスト教の遺産 ― 暦、祝祭、建造物、芸術遺産、民衆表現など ― に染み付いていることは、疑いの余地がありません。しかし、歴史家が「キリスト教世界」と呼ぶ、古代末期からルネサンスまでの1000年間、キリスト教とヨーロッパ社会の融合を象徴する時代は、果たして最も深い意味でキリスト教的だったのだろうか。つまり、キリストのメッセージに忠実だったのだろうか。熱烈で苦悩に満ちたキリスト教思想家、セーレン・キェルケゴールにとって、 「キリスト教のすべては、人類が立ち直り、キリスト教を排除しようとする努力にほかならない」。このデンマークの哲学者が的確に強調しているのは、イエスのメッセージは道徳、権力、そして宗教を完全に覆すものであるということだ。なぜなら、それは愛と無力さを何よりも優先するからである。キリスト教徒はすぐに、それを思想と伝統的な宗教的慣習の枠組みの中に再記述することで、人間の精神により合致したものにしようとした。この「キリスト教」の誕生、そして4世紀、政治権力と混同されて信じられないほど歪められたことは、しばしば、そのインスピレーションの源となったメッセージとは正反対のものである。教会は、イエスが制定した唯一の秘跡(聖体)を通してイエスの記憶とその臨在を伝え、イエスの言葉を広め、そして何よりもそれを証しする使命を持つ弟子たちの共同体として必要です。しかし、教会法、尊大な礼儀作法、偏狭な道徳主義、ピラミッド型の教会階層、秘跡の増殖、異端との血みどろの戦い、そして聖職者による社会への支配とそれに伴うあらゆる過剰な支配の中に、どうして福音のメッセージを見出すことができるでしょうか。キリスト教は大聖堂の崇高な美しさですが、同時にこれらすべてでもあるのです。第二バチカン公会議の教父は、キリスト教文明の終焉を前にして、 「キリスト教国は死んだ。キリスト教万歳!」とた。死の数年前にこの逸話を私に語ってくれたポール・リクールは、こう付け加えました。 「むしろこう言いたい。『キリスト教は死んだ。福音万歳!』。なぜなら、真にキリスト教的な社会は存在したことがないからだ。」キリスト教の衰退は、キリストのメッセージが再び聞かれる機会となるのではないでしょうか。 「新しいぶどう酒を古い皮袋に入れてはならない」とイエスは言われました。キリスト教会の深刻な危機は、福音書に記された生きた信仰の新たなルネッサンスへの序章と言えるかもしれません。隣人愛を神の愛のしるしとして捉えるこの信仰は、現代の価値観の基盤となっている人権を重視する世俗的ヒューマニズムと深く結びついています。そして、ますます非人間化していく世界の物質主義的・商業主義的衝動に対する、激しい抵抗の力ともなるでしょう。このように、私たちの「キリスト教文明」の廃墟から、キリスト教の新たな顔が生まれる可能性があり、キリスト教文化や伝統よりも福音に愛着を持つ信者たちは、この新たな顔に郷愁を抱くことはないでしょう。
*キリスト教がなぜスキャンダラスなのか(Seuil、2010 年)。
